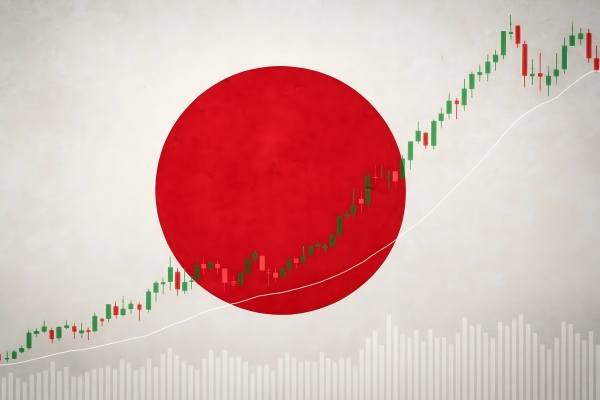取引
EBCについて
公開日: 2025-11-26
更新日: 2025-11-27
日本円(JPY)対米ドル(USD)の為替レートが1米ドル≒155.7円程度と表示されているのを見たら、「このまま円安が進むのか、それとも反転して円高になる可能性はあるのだろうか?」と疑問に思うかもしれません。マクロ経済、中央銀行の政策、そして為替レートの要因という3つの側面から、今後の円高の可能性と動向を読み解いていきましょう。
マクロ経済情勢
まず、最新のデータを見ると、日本のインフレ率は改善しているものの、賃金上昇率はそれに追いついていないことが分かります。9月の日本のコア消費者物価指数(CPI)は前年比約2.9%上昇し、日本銀行の目標である2%を上回りました。しかし、同時期の名目賃金は約1.9%上昇にとどまり、実質賃金(インフレ調整済み )は依然として約1.4%下落しています。
これは、家計の購買力が真に改善していないことを意味し、結果として消費支出が不十分となり、経済成長を阻害する可能性があります。インフレ圧力と賃金上昇率のミスマッチは、円の為替レートに影響を与える重要な要因です。
中央銀行の政策展望
第二に、日本銀行の金融政策について見てみると、政策金利は約0.5%に引き上げられているものの、依然として非常に緩和的な状況にあります。日銀総裁は、2%のインフレ目標に近づく兆候は見られるものの、「賃金・物価スパイラル」による持続的な上昇傾向はまだ完全には確立されていないと指摘しました。
したがって、日本銀行が金融政策の正常化を目指すとしても、そのペースは非常に慎重なものとなるでしょう。これはまた、短期的には円高を強く支える材料が不足していることを意味しています。
為替レートと米ドル
為替レートと米ドルの動きを見てみましょう。米ドル/円は現在157円前後で推移しており、過去1年間で一時139円前後まで下落し、158円を突破したこともありました。米ドル高、米国経済指標、そして連邦準備制度理事会(FRB)による利下げ期待は、いずれも米ドル/円に大きな影響を与えるでしょう。
米ドルが堅調に推移すれば、円は下落圧力にさらされるでしょう。一方、米国経済が減速し、金利が引き下げられれば、金利差の縮小によって円は緩やかに上昇する可能性があります。

円の将来動向分析
上記を踏まえ、円高の行方について、以下の分析が示唆します。
緩やかな円高の可能性あり
日米金利差は徐々に縮小する可能性がある。米国経済が減速し、利下げに転じる可能性がある一方で、日本ではインフレと賃金上昇のスパイラルが見られる場合、中央銀行は緩やかに金利を引き上げるとみられます。
金利差の縮小は、特にドル安を背景に、一般的に円高を後押しします。
大幅な円高は考えにくい
日本の経済成長は弱く、実質賃金は低下しており、中央銀行の政策正常化は緩やかです。
米国経済は依然として底堅く、ドル高をめぐる不確実性が存在するため、これらの要因が円高になる可能性を限定しています。
円高と円安を左右する主要な変数は以下のとおり
米国が予想通り利下げに踏み切るかどうか。
日本銀行が予想外に利上げに踏み切るかどうか。
世界規模または日米間で、大きな貿易ショックや地政学ショックが発生するかどうか。
米国経済が好調を維持し、ドル高が続く場合、円安が進む可能性があります。逆に、米国経済が弱まり、ドル安が進み、日本が賃金上昇とインフレのスパイラルを経験する場合、円はさらに上昇する可能性があります。
総合評価
現在のデータと状況に基づくと、今後数ヶ月間、円は急激な反発よりも緩やかな上昇を経験する可能性が高いです。具体的には、米ドル/円は現在の157円前後から140~150円の範囲へと徐々に下落する可能性があります。より低い水準(例えば130円未満)に到達したり、急激な円高に転じたりするには、「加速シナリオ」が必要となります。
逆に、米ドルが上昇したり、日本経済が予想外に悪化したりした場合、円安が続く可能性があります。
一般的に、円高は構造的な論理(金利差の縮小、インフレ率の目標達成への接近、中央銀行による超緩和的な金融政策からの段階的な離脱)によって支えられているものの、複数の逆風(経済成長の鈍化、実質賃金の低下、政策実施の遅れ、米ドルおよび世界の資本フローの影響)によって制約されています。
投資家や観測者は、円の動向を注視する際に、以下の指標に細心の注意を払うべきです。
日本の賃金上昇率は加速しているか?
コアインフレ率は高止まりしているか?
日銀の金利とバランスシート政策
米国経済とドルの動向
これらの主要要因を継続的に監視することは、将来円高になる可能性と上昇ペースをより正確に判断するために不可欠です。
免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。