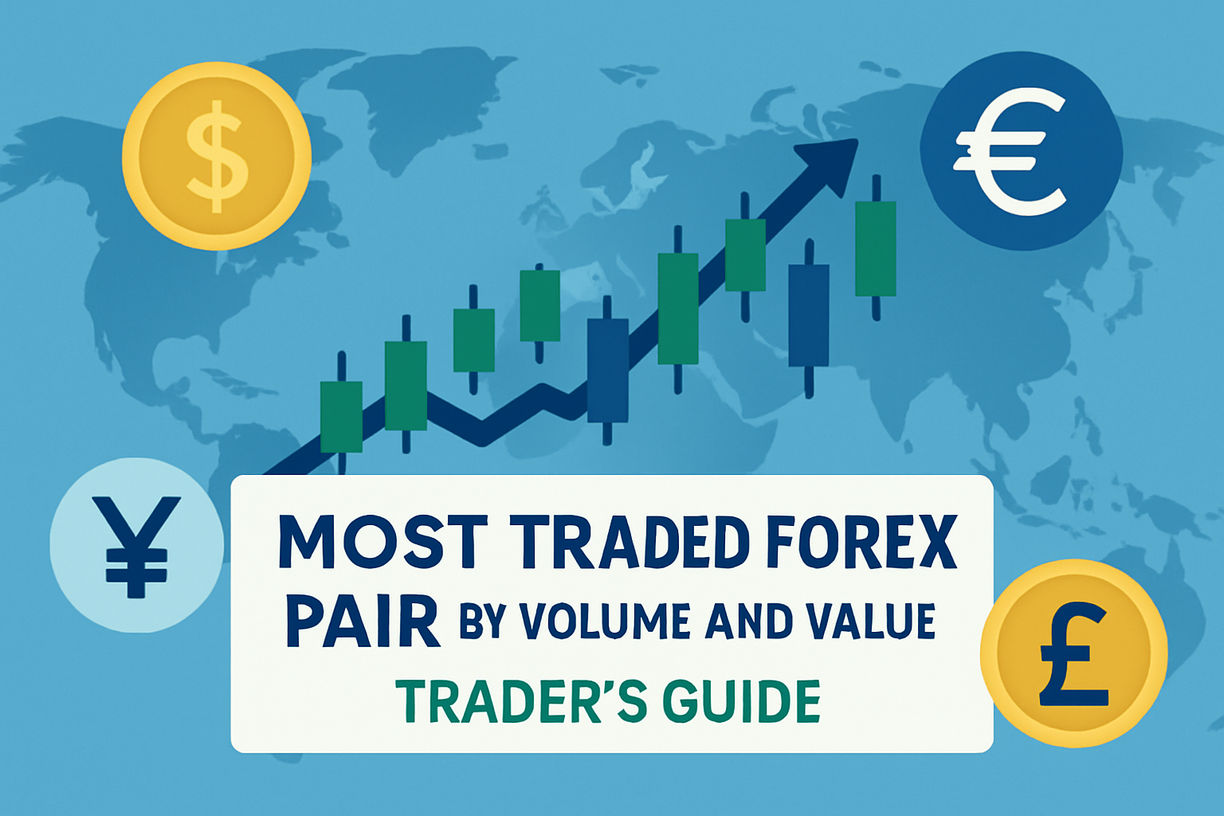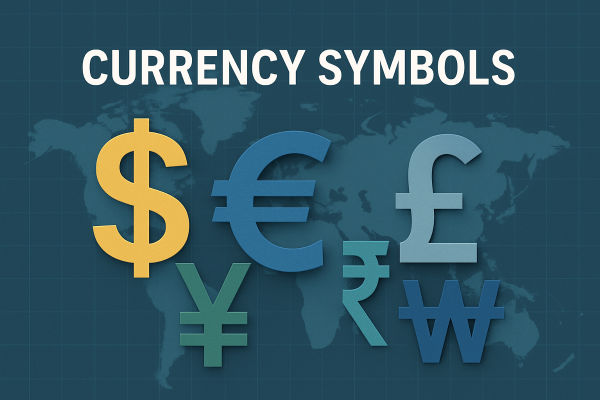取引
EBCについて
公開日: 2025-11-06
近年、日本と中国の経済関係が一段と密接になり、両国間での貿易量が増加しています。これに伴い、ドルを介さずに円と人民元を直接交換する取引(直接決済)が拡大しており、為替市場での注目度も高まっています。
一方で、円安と人民元安が同時に進行する「二重通貨安」という特殊な状況が続いており、企業の輸出入コストや投資判断に影響を与えています。そのため、今後の円/人民元レートの動きは、日本企業・投資家にとって重要な関心事となっています。
現在の円/人民元レートの動向

現在、円/人民元レートは1人民元=約21円前後で推移しており、2024年以降は比較的安定したレンジ相場が続いています。ただし、背後では両国の金融政策や米ドルの動向によって微妙な変動が見られます。
過去1年間の動きを見ると、2024年前半には円安・人民元安が同時に進行し、為替レートは一時22円を超えました。しかし、その後は日銀による金融政策修正への期待感や、中国当局による元防衛策の強化が影響し、円高・元高方向に小幅な反発を見せています。過去3年のスパンでは、2022年の中国ロックダウン期に一時的な元安が進み、その後2023〜2025年にかけて緩やかな回復基調にあります。
2024〜2025年にかけての主な変動要因は以下の3点です。
日銀の金融政策(マイナス金利解除の動き)
日銀は長年続いたマイナス金利政策を段階的に修正する姿勢を示しており、これが円高圧力となっています。ただし、急激な利上げを避ける慎重な姿勢が続いており、円の上昇スピードは限定的です。
中国人民銀行の為替安定化政策
人民銀行は元安の過度な進行を抑えるため、為替レートの安定を重視する介入姿勢を維持しています。特に2024年以降、対ドルでの元安が進む中でも、「管理された安定」を維持する姿勢が明確になっています。
米ドルの影響(ドルインデックスとの相関)
円も人民元もドルに対して相対的な通貨であるため、ドルインデックスの動きが両通貨に直接的な影響を与えます。米国の利下げ観測が強まるとドル安が進み、相対的に円・元が買われやすくなりますが、米国経済が強い場合は再びドル高基調が続き、円・元ともに下押しされやすくなります。
円/人民元レートは短期的には「安定したレンジ内の揺れ」が続く見通しですが、日中両国の金融政策転換のタイミング次第で、中期的には変動幅が拡大する可能性があります。
為替レートに影響する主な要因

円/人民元の為替レートは、単なる通貨需給だけでなく、経済指標・政策・国際関係など、さまざまな要素が複雑に絡み合って動いています。特に日中両国の経済規模が大きいため、為替の変動はアジア全体の資金フローにも影響を及ぼします。
■ 経済ファンダメンタルズ
日本と中国の経済成長率・インフレ率・貿易収支の差は、円/人民元レートに大きな影響を与えます。
中国は依然として世界第二位の経済大国であり、製造業と輸出の比重が高い一方、日本は内需と技術産業中心の構造です。
日本のインフレ率は上昇傾向にあるものの、依然として欧米より低水準。一方、中国ではデフレ懸念が残り、需要低迷が人民元安要因となっています。
両国のGDP成長率の差が縮まると、相対的に円の価値が安定しやすくなります。
■ 金融政策の方向性
日銀と中国人民銀行(PBOC)の政策姿勢の違いも重要な決定要因です。
日本銀行(日銀)は長期にわたる金融緩和からの脱却を模索中で、マイナス金利の解除や長期金利の上昇が焦点です。これが進めば円高要因となります。
一方、中国人民銀行(PBOC)は景気刺激を優先し、利下げや預金準備率の引き下げを継続しています。これが人民元安につながる一方、当局は「過度な元安」を防ぐため為替市場への介入を行っています。
結果として、両国の政策方向の「すれ違い」が円/人民元の短期変動を生みやすい状況です。
■ 地政学的要因(米中関係・日中関係)
為替市場では、地政学リスクも無視できません。特に日中双方にとって米国との関係が影響を及ぼす構造です。
米中関係の緊張:貿易摩擦や技術規制が強化されると、中国経済への不透明感が高まり、人民元売りが進む傾向があります。
日中関係の微妙なバランス:政治的には領土問題や安全保障で対立する場面もありますが、経済面では依存度が高く、「政治的緊張 × 経済的協調」という複雑な関係が続いています。
また、台湾情勢や南シナ海の動向など、アジア地域の地政学的リスクが高まると、投資家は安全資産として円を買う傾向にあり、円高が進みやすくなります。
■ 投資・資金フローの動き
外国人投資家の動向や資本移動も円/人民元に影響します。
日本の株式市場や国債が海外投資家に買われると、円需要が高まりやすい。
一方、中国では海外資本の流出入規制や投資信頼感の低下が人民元売り要因になることがあります。
グローバル投資家がリスクを取る局面では新興国通貨(人民元)が買われ、リスク回避局面では円が買われやすく、これが円/人民元レートの短期的な方向感を左右します。
円/人民元の為替レートは、経済・政策・地政学が三位一体で作用する通貨ペアです。特に今後は、日中関係の安定度合いと両国の金融政策転換のタイミングが、相場を左右する最大のカギとなるでしょう。
今後の見通し(2025年以降)
2025年以降の円/人民元レートは、日中両国の金融政策と景気動向の差によって方向性が大きく左右されると見られています。
現時点では、アナリストの多くが「短期的な安定・中期的な変動拡大」という見方を示しています。つまり、2025年前半はおおむね21円前後のレンジで推移する一方、年後半以降は政策転換や外部要因により振れ幅が広がる可能性があります。
■ アナリスト予測・市場コンセンサスのまとめ
多くの金融機関(例:野村證券、みずほリサーチ、中国工商銀行など)は、2025年の円/人民元レートを「20.5〜22.0円」程度と予想しています。
ただし、市場では円高方向へのポテンシャルを指摘する声が強く、日銀が年内に追加の利上げを行えば、一時的に20円を下回る可能性もあります。
一方で、中国の景気対策が強化され、内需回復が進めば、人民元の下支えとなり、レートが再び21〜22円台で安定する見方もあります。
■ シナリオ別見通し
【円高シナリオ】
主因:日銀の利上げ・米金利低下・中国景気の鈍化
日銀が2025年中に段階的な利上げを行い、金利差が縮小すれば、円買いが強まりやすくなります。
一方、中国では不動産市場の調整や輸出減速が続く場合、人民元が売られやすく、円/人民元は20円を下回る可能性も。
このシナリオでは、「金融引き締めの日本」対「景気刺激の中国」**という構図が明確化します。
【人民元高シナリオ】
主因:中国の内需回復・資本流入の拡大・日銀の緩和姿勢維持
中国が積極的な財政出動やテクノロジー分野の投資拡大で内需が回復すれば、人民元への信認が回復。
海外からの投資流入(債券・株式市場への資金回帰)も人民元高を後押しします。
一方、日銀が金利上昇を抑え、緩和的スタンスを続ける場合、円が売られやすく、レートは22円台後半へ上昇する可能性があります。
この場合、人民元は「アジアの安定通貨」として再評価される展開です。
【横ばいシナリオ】
主因:双方の金融緩和維持・ドルの安定・世界経済の減速
日本・中国ともに急な政策変更を避け、金融緩和を続ける場合、円/人民元は21円前後でのレンジ相場が続く見込み。
米ドルが安定すれば、ドルを介した間接的な影響も限定的になり、短期的には変動が小さくなります。
ただし、地政学的リスクや原油価格の変動が突発的な要因となる可能性もあり、完全な安定とは言えません。
■ 総合評価
2025年の円/人民元レートは、「円高リスクやや優勢、ただし上下にブレる余地」があると考えられます。
日中両国ともに経済構造の転換期にあるため、為替は一方向に動くよりも、政策と景気のバランスを反映する形で揺れ動く展開が予想されます。
特に、為替介入や政策発言といった当局の対応速度と透明性が、相場の安定性を左右する重要なカギとなるでしょう。
日本企業・個人投資家にとっての影響
円/人民元レートの変動は、日本の貿易企業・投資家・一般消費者にそれぞれ異なる影響を与えます。特に、日中経済の結び付きが深まる中で、為替の変動は企業収益や投資パフォーマンス、さらには観光・消費動向にも直接的に反映されるようになっています。
■ 日中貿易企業への影響(輸出入コスト)
日本企業にとって、中国は最大級の貿易相手国の一つです。円/人民元レートの変動は、輸出入コストや利益率に直結します。
円高が進む場合:
日本から中国への輸出品(自動車、精密機械、化学製品など)は価格競争力を失いやすく、輸出企業の採算が悪化します。一方、中国からの輸入品(電子部品、衣料品など)は安く仕入れられるため、輸入企業や小売業にとってはコスト低下のメリットがあります。
円安が進む場合:
逆に円安局面では、輸出企業は利益を拡大しやすくなります。特に中国市場で展開する自動車・機械メーカーは、円安による採算改善が期待されます。一方、輸入コストは上昇するため、小売業や製造業のコスト圧力が高まり、価格転嫁が課題となります。
また、近年では人民元建てで取引する日系企業も増えており、為替リスク管理の手法として「直接決済」や「通貨スワップ契約」が広く利用されています。こうした仕組みは、為替変動リスクの軽減に寄与しています。
■ 投資家視点でのチャンス(人民元建て資産・ETF)
円/人民元の為替動向は、個人投資家にとっても新たな投資機会をもたらしています。人民元の国際化が進むにつれ、投資手段も多様化しています。
人民元建て債券(点心債)や国債ETF:
人民元が安定・または上昇局面に入ると、人民元建て債券やETFが魅力的になります。特に中国政府債券は比較的高い利回りを維持しており、円安+元高の局面では為替差益も期待できます。
中国株・香港市場への間接投資:
中国の内需拡大政策が進む場合、消費関連やテクノロジー関連株に投資するETFも人気です。人民元の安定が続くと、外国人投資家の資金流入が増え、株価上昇の追い風となる可能性があります。
リスク要因:
ただし、人民元市場は依然として資本規制や当局の介入が存在し、自由度が低い点に注意が必要です。投資を行う際は、為替ヘッジを活用した分散運用が推奨されます。
■ 観光・消費分野での為替効果
為替レートは観光や消費にも直接的な影響を及ぼします。
円安局面では:
中国からの訪日旅行者にとって、日本での購買力が高まり、インバウンド消費(家電・化粧品・ブランド品など)が増加します。これにより、観光業界・小売業界にはプラス効果が生まれます。
円高局面では:
逆に日本人の中国旅行や中国製品の購入がしやすくなり、個人消費の一部が海外に流れる傾向があります。特に円高による越境ECの拡大が進む可能性もあります。
為替安定が続く場合:
観光・貿易・消費のバランスが取りやすくなり、企業や消費者が為替変動に左右されにくい安定した環境を享受できます。
円/人民元のレート変動は、企業活動・投資戦略・消費行動のすべてに影響する重要なファクターです。今後の動きを見据え、企業は為替リスク管理を強化し、個人投資家は長期的な視点で人民元資産をどう組み込むかを検討することが求められます。
今後のチャレンジとリスク要因
今後の円/人民元レートには、いくつかの重要なリスク要因が存在します。
まず、中国経済の減速懸念が最大の不安材料です。不動産市場の低迷や輸出の伸び悩みが続けば、人民元安が進みやすくなります。
次に、日本の金利政策転換リスクです。日銀が予想より早く利上げに踏み切った場合、急激な円高につながる可能性があります。
また、両国政府が市場の過度な変動を抑えるために為替介入を行う可能性もあり、そのタイミング次第で相場が一時的に大きく揺れることがあります。
さらに、地政学的リスク(台湾情勢や米中対立の緊張)が高まれば、安全資産としての円買いが強まり、一時的に円高方向へ動くリスクもあります。
これらの要因を総合すると、2025年以降の円/人民元市場は「安定と変動の綱引き」が続くと予想されます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 円/人民元の取引はどこでできますか?
円/人民元の取引は、主に外国為替市場(FX市場)や銀行の外貨取引口座で行うことができます。
個人投資家であれば、FX会社が提供するクロスレート(円と人民元の直接取引)を通じて売買が可能です。国内では、SBI FXトレードやGMOクリック証券など一部の業者が人民元建て取引に対応しています。
一方、企業間では、日本国内の主要銀行(三菱UFJ・みずほ・三井住友など)が提供する「円/人民元直接決済サービス」を利用できます。これにより、ドルを介さずに円⇄人民元を直接交換でき、為替コストの削減や決済スピードの向上が実現します。
Q2. ドルを介さない決済のメリットは?
円と人民元を直接交換する「直接決済」の最大のメリットは、コスト削減とリスク低減です。
従来、日中間の貿易では「円→ドル→人民元」という二段階の為替変換が必要でした。この場合、ドルの為替手数料やスプレッドコストが発生します。
しかし直接決済では、この中間コストを省くことができ、企業の決済コストを数%削減できるケースもあります。
また、ドルの変動に左右されにくくなるため、為替リスクの分散という点でも大きなメリットがあります。特に、日中間貿易が拡大する中で、こうした「脱ドル化」の動きは今後さらに進むと見られています。
Q3. 人民元の国際化はどこまで進んでいますか?
人民元の国際化はここ数年で大きく進展しています。
国際決済銀行(BIS)やSWIFTのデータによると、人民元はすでに世界で5番目に多く使われる決済通貨にまで上昇しており、香港、シンガポール、ロンドンなどの主要金融センターでも利用が拡大しています。
また、中国は「一帯一路」構想を通じて、アジア・中東・アフリカ諸国との人民元建て貿易や融資を増やしており、人民元の国際的なプレゼンスが着実に高まっています。
さらに、人民元建ての国債・社債市場も拡大しており、外国人投資家が中国債券を保有する比率も上昇傾向です。
ただし、完全な自由化まではまだ時間がかかると見られており、中国国内の資本規制や外貨送金制限が残ることから、人民元は「管理された国際通貨」という位置づけにあります。
結論:円/人民元の今後をどう見るか
現時点では、円/人民元レートはやや円安方向で推移しており、日本の金融緩和継続と中国の経済政策がバランスを取る形となっています。
投資や貿易の観点からは、為替ヘッジの活用や、取引通貨の分散が引き続き重要です。
中長期的には、脱ドル化の流れや人民元の国際化の進展がレートに影響する可能性があり、アジア経済圏における通貨の役割変化にも注目すべき局面です。
免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。