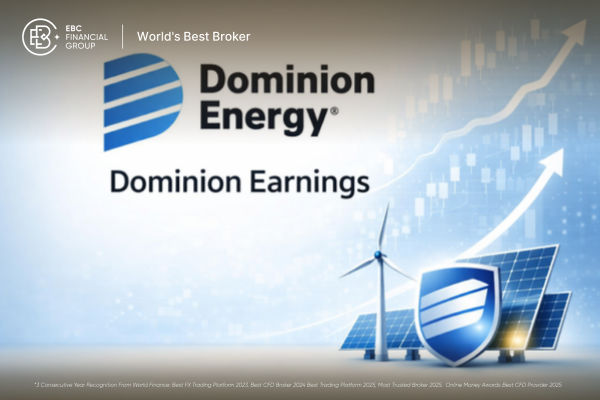取引
EBCについて
公開日: 2025-11-21
JT株は高配当で人気がありますが、長期投資としては注意点も多い銘柄です。まず、世界的に喫煙人口が減り続けており、たばこ市場は年々縮小しています。また、政府の規制や税金が強まっており、売上や利益が圧迫されやすい状況です。さらに、EPS(1株利益)の伸びが鈍く、企業成長が限定的という指摘もあります。
加えて、利益の多くを海外、特にロシアなどに依存しているため、為替や地政学リスクの影響を大きく受けやすい点も問題です。高配当で魅力的に見えますが、その裏側には事業構造の課題が潜んでおり、「配当が続くのか?」という懸念も残ります。
JT株を買ってはいけない理由、そして本当に買うべきではないかを詳しく解説します。

理由①:たばこ市場が世界的に縮小し続けている
JT株を買ってはいけない理由の一つに、「たばこ市場が世界的に縮小し続けている」という構造的なリスクがあります。まず、日本国内では喫煙率が着実に低下しており、厚生労働省の2023年国民健康・栄養調査によると、習慣的に喫煙している成人の割合は 15.7%(男性25.6%、女性6.9%)まで下がっています。これは過去10年で有意に減少している傾向です。
世界的にもたばこ使用量は減少傾向にあり、WHOの報告によれば、かつては成人の3人に1人がたばこを使用していたのが、現在では約5人に1人にまで落ちています。 このようなグローバルな縮小トレンドは、JTの基盤となるたばこ事業そのものへの長期的な逆風になり得ます。
また、紙巻きたばこだけでなく、加熱式たばこ(加熱型タバコ)が成長しているものの、それ自体にも限界があります。日経POS情報の分析では、加熱式たばこが売上面で従来のたばこを上回ってきたものの、たばこ全体の販売数量は年々減少傾向にあり、たばこ市場全体が縮小しているという指摘があります。加熱式たばこへの移行が進んでも、それがたばこ市場全体の縮小を補えるかは不透明というわけです。
つまり、JTにとって「売り上げを支えるたばこ市場」が、国内外ともに縮小圧力にさらされており、高配当を出していても長期的な成長力には疑問が残る、という指摘があるのです。
理由②:世界的な規制強化に晒されている
JT(日本たばこ産業)が投資リスクとされる大きな理由の一つに、たばこ業界をめぐる 規制強化の進行 が挙げられます。これは、日本国内だけでなく、国際市場においても無視できないマクロリスクです。
まず、JT自身の統合報告書によれば、日本においては「たばこ広告および製品パッケージに健康警告表示を行う義務」があり、さらに警告文の表示面積は、最新の科学知見に合わせて 拡大されていると指摘されています。これは、パッケージが単なるブランドの媒体ではなく、警告メッセージの伝達手段として強く規制されていることを意味します。
加えて、広告に関しても JT のレポートでは自主規制強化が進んでおり、Tobacco Institute of Japan(TIOJ)のガイドライン改定で、未成年者(20歳未満)への広告露出を抑える規制が強まり、店舗での販売時の広告表示方法も制限されるようになっています。これにより、たばこ製品を宣伝する余地が狭まる可能性があります。
さらに、日本では 健康増進法の改正によって受動喫煙対策が強化され、公の施設や飲食店での喫煙スペースが減少傾向にあります。JTもこういった環境変化が「財務・営業面に影響を与える可能性を認識している」と述べています。
国際的にもリスク要因があります。JTの報告書では、欧州や米国を中心に「RRP(Reduced-Risk Products:リスク低減製品)」の規制が多様化しており、国によっては加熱式たばこなどに対するフレーバー禁止や別規制 がすでに導入されていると説明されています。例えば、EUでは一部フレーバー製品の禁止規制が加熱式たばこにも適用されており、米国でも特定のフレーバー電子たばこの販売が制限されています。
これらの規制強化によって、JTはたばこ製品のパッケージデザイン、広告展開、販売方法すべてに対してコストや制約が増す可能性があり、将来的な収益を圧迫するリスクが高まっていると言えます。
理由③:世界的な規制強化に晒されている
JTはロシア事業への依存度が非常に高く、これが大きな投資リスクとされています。実際、JTのロシア事業は利益の 約20% に相当するという報道があり、経営のかなり重要な柱になっています。
また、ロシアではJTが工場を4か所保有し、4.000人以上の従業員を抱えているなど、事業の深さが窺えます。
しかし、こうした高い依存は 政治リスク と 制裁リスク を伴います。JTは西側諸国の対ロシア制裁に対応するため、サプライチェーンの再構築を進めており、トルコ経由で物資を送る構造を作っています。
さらに、経営や意思決定に関わる人材の配置も見直しており、制裁対象国との関係を避ける形で役員・社員を香港に配置しているという報告があります。
これだけロシアに依存していると、 為替リスク も無視できません。ロシア事業での利益はルーブル建てで出ている部分がある可能性があるため、ルーブルの価値変動や円との為替変動がJT本体の収益に大きく影響します。加えて、国際関係が悪化すれば、事業の継続や撤退の選択を迫られる可能性もあります。
実際、JTはロシアでの新規投資・マーケティング活動を停止したと発表しています。一方で、撤退までは踏み切っておらず、「最悪の場合には売却する可能性もある」とCEOは述べていますが、現時点では継続が基本戦略です。
さらに、中長期的な懸念としては、国際環境の悪化や制裁の強化によってロシア事業からの収益が不安定化する可能性があり、これがJTの業績や配当政策にマイナス影響を及ぼすリスクは無視できません。
理由④:高配当だが、減配リスクがゼロではない
日本たばこ産業(JT)は長年、高配当を維持する方針を取っており、配当性向(利益に対してどれだけ配当を出しているか)は おおよそ75% を目安にしていると公表しています。
しかし、この配当性向の数字には注意が必要です。
まず、JTの 2024年度の連結ベース配当性向は報告上 192.2% に達しており、一見すると非常に高い水準です。これは、カナダでの訴訟に関する引当金などの特殊要因を除いた「調整後」の数字でも 74.3% に相当します。
つまり、純利益ベースではかなり無理のない配当性向に抑えようとしているものの、訴訟リスクなどが業績に影響を与えると、配当維持に対する負荷が大きくなり得るというわけです。
また、キャッシュフローの面でも懸念があります。JTはたばこ事業という成熟産業を主力としているため、営業キャッシュフローは比較的安定して潤沢ですが、 2024年度のフリーキャッシュフローは前年から大きく減少しており、配当原資としてのキャッシュ余力が縮んでいるとの指摘があります。
このような状況で、高配当を続けるためには相当なキャッシュ創出力が求められます。
さらに、配当を維持するために 訴訟損失を引当ててなお内部留保や準備金を取り崩しているという分析もあります。例えば、Business Insider Japanの記事では、JTが「配当性向75%を目安にしながら非常に強力なキャッシュ創出力を持っているが、コストや一時的な損失の影響を受けやすい構造」だと指摘されています。
この構造は、「高配当=安心」というイメージとは裏腹に、業績悪化があった場合には配当を切る選択肢がより現実的になるリスクをはらんでいます。
加えて、Simply Wall Stの記事などでも、JTは「配当を支えるのに必要なキャッシュフローに対して支払いがかなり高い割合」を使っており、長期保有目的で配当だけを目当てに急いで買うのは慎重になるべきという警告があります。
実際、過去には配当の調整(減配)を経験しており、株主にとっては「累進配当(利益が増えれば配当も必ず上がる)」というよりも 「業績次第」の面が強い、という見方もあります。
最後に、訴訟リスクも大きな不確実性要因です。たばこ産業では健康被害に関する集団訴訟が常につきまとうリスクがあり、JTも過去に大きな引当を計上しています。
このようなコストが今後さらに発生し、予想外に膨らんだりすれば、利益を圧迫し、配当を維持するための財務的な柔軟性が失われる可能性があります。
理由⑤:ESG投資で敬遠されやすい(株価の構造的重し)
JT(日本たばこ産業)は、たばこ産業という性質上、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資から敬遠されやすいという構造的なリスクがあります。具体的には以下のような点が指摘されています。
まず、ネガティブ・スクリーニング(除外型)を採用するESGファンドが多く、たばこ産業をポートフォリオから除外する傾向があります。たとえば、ロベコ(Robeco)はたばこ業界をESG投資の除外対象にしており、その結果、たばこ企業への投資割合を引き下げています。
また、国際的な指標プロバイダーである MSCI もたばこ企業を除いた指数を設定しており、その指数を使うETFや機関投資家はJTのような銘柄を組み入れにくくなっています。
さらに、資産運用会社AXA IMも、ESG・責任投資方針の中でたばこ会社を除外対象にしており、ESGカテゴリー(特にEUのSFDRに関わるファンド)ではたばこを除く方針を明確に打ち出しています。
こうしたESG除外ポリシーをとる大手運用機関が多いため、国際機関投資家からの資金流入が限定される可能性があるわけです。
また、ESGリスク評価の観点でも、JTには注意が必要な点があります。たとえば、GXリサーチによると、JTは Sustainalytics によるESGリスク評価で「ミディアムリスク」とされており、ESG課題への対応が評価されているものの、それでもリスクがゼロではないと見なされています。
こうした評価は、ESG重視の投資家にとってマイナス要因になり得ます。
結果として、ESG投資家の資金がそもそもJTに流れにくい構造が存在し、これはJTの株価の上昇余地にとって構造的な重しになり得ます。ESG投資の潮流が強い中で、たばこ企業という属性を持つJTは、特定の国際資本やETFから不利な扱いを受けやすい、というのが懸念点です。
JT株を買うメリット(反対意見)

高配当利回りが非常に魅力的
JTは長らく高配当銘柄として支持されており、2025年12月期には配当を 年208円(=利回り約4.8%)に増配する見込みと発表されました。
この配当利回りは、配当重視・インカム投資をする投資家にとって大きな魅力です。
強力なキャッシュ創出力(キャッシュカウ的性質)
Business Insiderによれば、JTは非常に強いキャッシュフローを持っており、これが高配当を支える源泉になっているとのことです。
また、JTの内部報告でも、配当性向を「利益の75%を目安」にして中長期で株主還元を重視する方針が明示されており、キャッシュ創出をビジネスへの再投資と還元のバランスを取ろうとしています。
実際、JTの2023年のフリーキャッシュフローは 443.7 億円と報告されており、一定の余力があります。
加熱式たばこ(Reduced-Risk Products:RRP)への積極投資
JTのCFOメッセージによると、2025〜2027年にかけて 6500億円規模の戦略投資を予定しており、その中心は加熱式たばこ(HTS)などのRRP事業です。
これにより、規制や市場の変化に備えつつ、新たな成長分野を確保しようとしています。
将来的なキャピタルゲインの可能性
Finaseeの分析によれば、JTの株価は過去5年で上昇しており、売却益(キャピタルゲイン)と配当(インカムゲイン)の両方を狙える「一挙両得」のポテンシャルがあると指摘されています。
特に中長期で株を保有しながら配当を得る投資家にとっては、安定した収益源として魅力があります。
財務の安定性と資本還元方針
JTは財務面でも健全性を保っており、配当支払い・自社株買いといった財務キャッシュフローの管理もしっかりしているという分析があります。
また、高配当を支えるだけでなく、将来的な利益成長も見据えており(加熱式事業への投資を通じて)、株主還元の継続性を重視しています。
JT株を買ってはいけない投資家のタイプ
JT株は安定配当が魅力ですが、すべての投資家に適した銘柄とは言えません。まず、高い成長性を求める投資家には向いていません。たばこ産業は世界的な規制強化や市場縮小の影響を受けており、急速な株価上昇や事業拡大は期待しづらいため、短期的な値上がり益や成長株を求めるタイプには不向きです。
また、ESG(環境・社会・ガバナンス)を投資基準として重視する投資家にも、JT株は避けられやすい銘柄です。たばこ事業は健康被害や社会的責任の観点からネガティブ要素が強く、国際的なESG投資基準でも除外対象となるケースが多いためです。
さらに、規制リスクを避けたい投資家にも適していません。JTが属するたばこ業界は法整備や広告規制、増税リスクが常に存在し、事業環境が政治・政策に大きく左右されます。将来の収益性が読みづらい点は、リスク許容度が低い投資家にとって不安材料となります。
加えて、為替や地政学リスクに敏感な投資家にも注意が必要です。JTの収益の多くは海外事業に依存しており、円高局面や国際情勢の変化が業績へ直接影響します。特に戦争・制裁・経済制限などは、想定外の損失につながる可能性があります。
JT株を買う前にチェックすべきポイント
JT株を購入する前には、投資判断を誤らないためにいくつかの重要な指標や情報を確認することが必要です。
配当性向・キャッシュフロー
JTは高配当を維持していることで知られますが、その持続可能性を判断するには 配当性向(利益に対する配当割合) や 営業キャッシュフロー、フリーキャッシュフロー を確認することが重要です。配当性向が高すぎる場合、業績悪化時には減配リスクが増大します。
海外依存度の確認
JTは国内市場だけでなく海外市場からも多くの収益を得ています。特にロシアや東南アジア市場への依存度は高く、地政学リスクや為替リスクの影響を受けやすい点に注意が必要です。海外事業の比率や地域別の売上構成をチェックすることで、リスクの大きさを把握できます。
規制の最新動向
国内外でのたばこ規制の動きは、JTの収益に直結します。パッケージの警告表示強化、加熱式たばこの規制、増税など、最新の法改正や規制状況を把握することで、将来的な売上や利益への影響を予測しやすくなります。
喫煙人口データ
国内外の喫煙人口の推移も重要な指標です。日本国内では喫煙率が年々低下しており、海外でもWHOの統計などで成人喫煙率が減少傾向にあります。市場自体が縮小している中で、JTが成長性を維持できるかを考えるうえで参考になります。
ROE/EPS推移
企業の収益性や株主還元力を評価するために、自己資本利益率(ROE) や 1株あたり利益(EPS) の推移を確認することも重要です。ROEが安定して高水準であれば、効率的に利益を株主に還元していることが分かり、長期保有を検討する材料となります。
よくある質問
Q1:JT株は高配当だから安心ですか?
JTは長年にわたり高配当を維持していますが、たばこ業界は規制強化や市場縮小の影響を受けやすく、将来の利益や配当が必ずしも安定するとは限りません。高配当は魅力ですが、リスクを理解したうえで投資判断を行う必要があります。
Q2:JT株は長期投資に向いていますか?
配当重視の長期投資には一定の魅力があります。特に、安定したキャッシュフローを持つため、配当収入を狙う投資家には向いています。ただし、成長性の面では限定的で、株価上昇を大きく期待する投資家には不向きです。
Q3:海外事業への依存はリスクになりますか?
はい、特にロシアなど海外市場への依存が高く、為替リスクや地政学リスクの影響を受けやすい点が懸念材料です。海外売上の比率や主要市場の動向を確認することが重要です。
Q4:ESG投資家でもJT株は買えますか?
JTはたばこ事業の性質上、ESG投資ファンドでは除外されることが多いです。環境・社会面でネガティブ評価を受けやすく、ESG投資を重視する場合は注意が必要です。
Q5:JT株を買うならどの指標をチェックすべきですか?
配当性向、営業・フリーキャッシュフロー、ROE・EPSの推移、海外売上比率、規制や喫煙人口の動向などを確認すると、投資リスクを把握しやすくなります。
結論:本当にJT株を買ってはいけないか?
JT株は確かに高い配当利回りが魅力ですが、それが低リスクを意味するわけではありません。たばこ業界は規制強化や市場縮小という長期的トレンドに直面しており、将来的な収益や配当の安定性には注意が必要です。投資を検討する際は、「配当メリットが構造的リスクを上回るか」 を慎重に判断することが重要です。
免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。