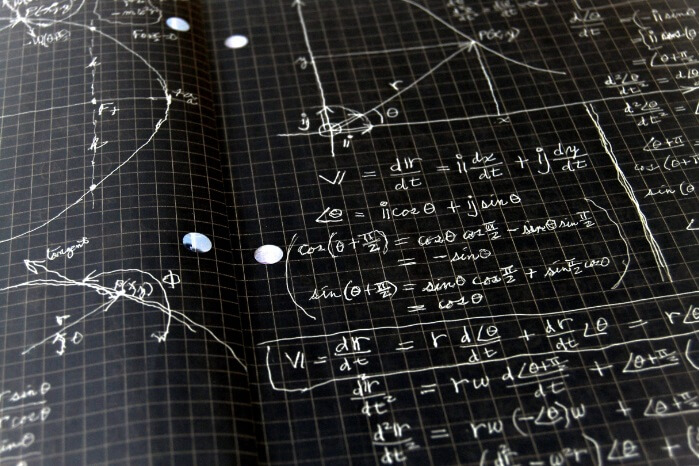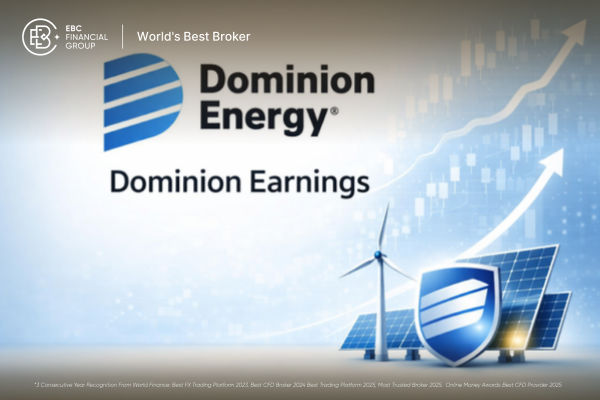取引
EBCについて
公開日: 2025-11-12
近年、金利上昇や円安、物価上昇といった環境の中で、安定した「インカムゲイン(配当収入)」を得たい投資家が増えています。その中でも、日本株の高配当ETFは、複数の高配当銘柄に分散投資できる点が大きな魅力です。
ETFは1本で多くの銘柄に投資でき、コストが低く、運用の手間が少ないのが特徴です。個別株のように企業ごとの業績変動リスクを気にする必要がなく、より安定した収益を狙える手段として注目されています。
日本株の高配当ETFの仕組みとメリット

高配当ETFとは、日経平均やTOPIXなどの指数をもとに、配当利回りが高い銘柄を選定して構成される上場投資信託(ETF)のことです。ETF(Exchange Traded Fund)は証券取引所に上場しており、株式と同じようにリアルタイムで売買できます。
多くの日本株の高配当ETFは、「日経平均高配当株50指数」や「MSCI日本高配当指数」などに連動しており、配当利回りの高い企業を中心に自動的に構成銘柄が入れ替えられます。これにより、投資家は個別銘柄を選ぶ手間なく、安定した配当を受け取る仕組みを構築できます。
1.メリット
① 分配金の安定性
ETFは複数の高配当株を組み合わせているため、個別企業の業績悪化による配当減少リスクを分散できます。結果として、年間を通じて安定した分配金を得やすくなります。
② 個別銘柄より低リスク
一社の値動きに依存せず、複数の業種に分散投資されているため、相場変動のリスクを抑えながら配当収入を確保できます。特に初心者や長期投資家に人気があります。
③ 自動リバランスによるメンテナンス不要
ETFは定期的に構成銘柄を見直す「自動リバランス」が行われるため、投資家自身が銘柄を入れ替える必要がありません。手間をかけずに最適な高配当ポートフォリオを維持できる点が魅力です。
2.デメリット
① 市場全体の下落には影響を受ける
ETFは株式市場全体に連動するため、景気後退や株価下落局面では価格も下がります。配当は安定しても、元本割れリスクはゼロではない点に注意が必要です。
② 信託報酬がかかる
ETFの運用には「信託報酬」と呼ばれる手数料が発生します。一般的には年率0.1〜0.3%程度と低コストですが、長期運用ではリターンに影響するため、コスト比較も重要です。
日本株の高配当ETFランキング
1.銘柄コード 1489/NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
本ETFは、「日経平均株価の構成銘柄のうち、予想配当利回りが高い原則50銘柄」で構成される「日経平均高配当株50(トータルリターン)指数」に連動することをめざして運用されています。
信託報酬(税込)は年0.308%です。
直近実績ベースの分配金利回り(過去12か月の実績分配金÷終値ベース)は約3.38%となっています。
年4回(1月、4月、7月、10月)に分配を実施しています。
構成銘柄例として、三菱商事・三井住友フィナンシャルグループ・伊藤忠商事など高配当が期待される大手銘柄が挙げられています(実際に採用銘柄は変更される可能性あり)。
2.銘柄コード 1478/iシェアーズ MSCIジャパン高配当利回りETF
本ETFは、「MSCIジャパン高配当利回り指数(配当込み)」に連動をめざすもので、配当性向や配当継続性、ROEや自己資本比率などの財務指標も選定基準に取り入れられており、単純な配当利回りの高さだけでなく、財務健全性も重視されています。
信託報酬(税込)は年0.209%です。
直近の実績分配金利回りとして約2.52%が示されています。
決算・分配頻度は年2回(毎年2月9日および8月9日)です。
構成銘柄例としてトヨタ・NTT・オリックスなどが挙げられ、高配当かつ財務健全な銘柄群で構成されていることが特徴です。
3.銘柄コード 1577/NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
本ETFは、「今期予想配当利回りが高い日本株70銘柄」を原則対象として、等金額型で構成する「野村日本株高配当70(配当含む)指数」に連動をめざすものです。
信託報酬(税込)は年0.352%です。
直近実績分配金利回りは約3.26%というデータがあります。
年4回(1月、4月,7月,10月)に分配を行っています。
構成銘柄例としてキヤノン・三井物産・日本たばこ産業(JT)などが挙げられており、70銘柄とやや幅広いため「分散」を意識した設計とも言えます。
4.銘柄コード 1698/上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)
本ETFは「東証配当フォーカス100指数」に連動。こちらは、東証上場銘柄のうち「時価総額および予想配当利回り」に着目して選定された100銘柄(株式約90銘柄+REIT約10銘柄)で構成されます。
信託報酬(税込)は年0.308%です。
直近分配金利回りは約3.41%という報告があります(2025年6月30日時点資料)。
分配は年4回(1月、4月、7月、10月)となっています。
構成銘柄例として、KDDI・出光興産・オリックスなどが挙げられており、REITも含まれることで配当収入構造のブレを抑える設計とされている点が特徴です。
日本株の高配当ETFの選び方と活用戦略
日本株の高配当ETFを選ぶ際には、単に「利回りの高さ」だけに注目するのではなく、分配実績の安定性や信託報酬、構成銘柄のバランス、流動性といった複数の要素を総合的に判断することが重要です。
まず、【利回り】は投資判断の中心的な指標ではありますが、一時的に高い配当を出している企業が多く含まれるETFは、翌年以降の分配金が減るリスクもあります。そのため、過去数年にわたって安定した分配を行っているETFを選ぶことで、長期的なインカムゲインの安定性を高めることができます。
次に、【信託報酬】の低さも見逃せません。高配当ETFは長期保有を前提にする投資が多いため、年0.1〜0.3%程度のコスト差が数年後には大きなリターン格差に繋がります。特に、NEXT FUNDSシリーズやiシェアーズシリーズは業界でも低水準の信託報酬を実現しており、コストパフォーマンスの高さが際立っています。
また、【構成銘柄の業種バランス】も重要な視点です。高配当銘柄は商社、金融、エネルギー、通信といった業種に偏る傾向があるため、ETFによっては特定セクターに集中してしまう場合があります。ポートフォリオ全体で業種分散を意識することで、景気変動リスクを緩和することができます。
さらに、【流動性】が高いETFを選ぶことで、売買時のスプレッド(買値と売値の差)によるコストを抑えることができます。出来高が多く市場で活発に取引されているETFは、急な相場変動時でもスムーズに売買できる点で安心感があります。
次に、高配当ETFの【活用戦略】について見ていきましょう。
最も効果的な方法の一つは、配当金を再投資することで複利効果を狙うことです。受け取った分配金を再びETFに投資することで、時間の経過とともに資産が加速度的に増える「雪だるま効果」を得られます。
また、ETFによっては毎月や四半期ごとに分配金が支払われるものもあり、**定期的なキャッシュフローを得る「安定収入戦略」**としても活用できます。特に、定年後の生活資金やサイドインカムを目的とする投資家には適しています。
さらに、NISA口座(少額投資非課税制度)を活用することで、分配金や値上がり益にかかる税金を非課税にできます。特に「新NISA」では長期・積立枠の併用が可能になったため、配当再投資を行う長期投資との相性が非常に良い点が注目されています。
最後に、長期保有による「インカム+キャピタル両取り」戦略も効果的です。日本株の高配当ETFの中には、安定した配当を維持しながら基準価額も上昇しているものがあります。景気拡大局面では値上がり益(キャピタルゲイン)を得つつ、不況期でも配当収入でリスクを緩和できるという、バランスの取れた投資が可能です。
よくある質問
Q1:個別の高配当株とETF、どちらが有利ですか?
個別株とETFには、それぞれに明確なメリットとデメリットがあります。
個別の高配当株は、自分で企業を選定して投資するため、うまく選べば平均以上の配当利回りや株価上昇(キャピタルゲイン)を得られる可能性があります。しかし一方で、業績悪化や減配リスクを直接受けるため、銘柄選定の難易度が高く、分散が難しいという課題があります。
これに対し、高配当ETFは複数の高配当銘柄に自動的に分散投資できるため、特定企業のリスクを抑えながら安定した配当収入を得やすいという特徴があります。また、信託報酬も近年では0.2〜0.3%前後と低コストで、個別株を多数保有する場合と比べても管理の手間が少ない点が魅力です。
したがって、リスクを抑えつつ安定的なリターンを目指す投資家にはETFが有利といえるでしょう。
Q2:配当(分配金)はどのくらいの頻度で受け取れますか?
日本株の高配当ETFは、年2回または4回の分配を行うものが一般的です。
例えば、「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50(1489)」では年4回(1月・4月・7月・10月)の分配があり、定期的なキャッシュフローを重視する投資家に人気があります。
一方、「iシェアーズ MSCIジャパン高配当利回りETF(1478)」は年2回(2月・8月)の決算・分配形式を採用しており、シンプルに配当を受け取りたい長期投資家に向いています。
ETFによって分配方針は異なりますが、共通して言えるのは、個別株と同様に定期的なインカムゲインを得られるという点です。さらに、分配金を再投資すれば、複利効果による長期的な資産成長も期待できます。
Q3:円安や金利変動は高配当ETFにどのような影響を与えますか?
為替や金利の変動は、高配当ETFの構成銘柄に間接的な影響を与えます。
特に日本株の高配当ETFには、商社、輸出関連企業、銀行株などが多く含まれており、円安局面では輸出企業の利益が拡大するため、業績・配当の押し上げ要因となります。
実際、2023〜2025年の円安局面では、商社株や自動車株が好調で、それに連動する高配当ETFの分配金も増加傾向を見せました。
一方で、国内金利上昇は銀行や保険などの金融株にプラスに働く一方、電力・不動産セクターにはコスト増要因となる場合があります。したがって、ETFを選ぶ際は構成業種のバランスにも注意し、為替・金利環境の変化に応じて分散効果を活かすことが重要です。
結論
日本株の高配当ETFは、個別銘柄を選ばずに手間なく安定した収入を得たい投資家にとって最適な選択肢です。特に、分配金利回り・信託報酬・構成銘柄のバランスを比較しながら、長期保有による配当再投資効果を狙うことが重要です。
2025年に注目すべきETFとしては、
「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50(1489)」
「MAXIS 高配当日本株50 ETF(1577)」
「iシェアーズ MSCIジャパン高配当利回りETF(1478)」
が挙げられます。いずれも低コストかつ安定した配当実績を持ち、NISA口座での長期運用にも適した有力候補です。
免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。