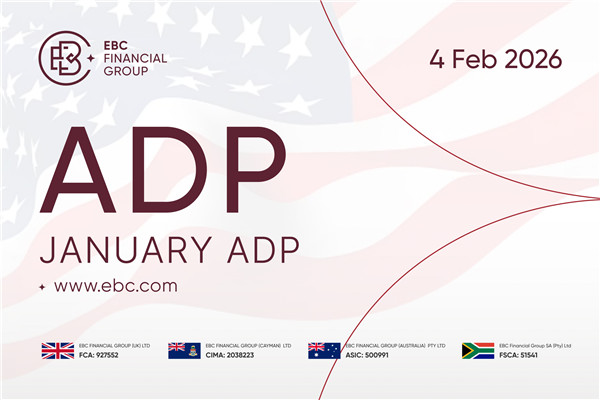取引
EBCについて
公開日: 2025-11-05
長期保有株とは、数年〜10年以上のスパンでじっくりと持ち続ける投資スタイルです。短期売買のように日々の値動きに一喜一憂する必要がなく、企業の成長とともに資産を育てられるのが特徴です。
最大の魅力は、「複利効果」と「配当再投資」による資産の雪だるま式成長です。長期的に保有することで、配当金を再投資しながら元本を増やし、時間を味方につけた安定した運用が可能になります。また、頻繁な売買が不要なため、取引コストや税負担も抑えられるというメリットもあります。
この投資スタイルは、忙しい社会人や安定志向の投資家に特に向いており、将来の資産形成や老後資金づくりにも効果的です。短期のトレンドではなく、企業の本質的な価値を見極めながら「じっくり育てる」姿勢がポイントです。

ランキング選定の基準
長期保有株を選ぶ際には、短期的な株価の上下に惑わされず、企業の基礎体力と持続的な成長力を重視することが大切です。ここでは、ランキングを作成する際に特に注目した5つの基準を紹介します。
①業績の安定性
長期保有において最も重要なのが、企業の業績が安定しているかどうかです。
売上や営業利益が毎年安定して伸びている企業は、景気変動に強く、株価の下落局面でも底堅さを発揮します。特に、5年以上連続で増収増益を維持している企業は、長期投資家から高く評価されます。
②配当利回りと配当性向
長期投資では「配当金」がリターンの大きな柱となります。
安定した配当利回り(一般的に3%以上が目安)を維持し、過去数年間で減配がない企業は信頼性が高いといえます。さらに、配当性向(利益のうちどれだけを配当に回すか)が極端に高すぎない(50%以下)企業は、将来の増配余地があり、長期的な資産形成に向いています。
③財務健全性
長期保有では、倒産や資金繰りの悪化といったリスクを避けることが重要です。そのため、自己資本比率が40%以上、負債比率が低い企業が理想的です。財務が安定していれば、景気後退局面でも耐久力があり、継続的な配当や成長投資が可能になります。
④成長性
安定性に加え、将来に向けて成長が見込めるかも大切な要素です。
中長期の事業戦略が明確で、AI・再生可能エネルギー・医療・半導体など成長産業に積極的に参入している企業は、株価上昇余地が大きくなります。単なる現状維持ではなく、「次の時代に強いビジネスモデル」を持っているかを見極めることがポイントです。
⑤株主還元姿勢
企業がどれだけ株主を大切にしているかも、長期投資家にとって重要な判断基準です。
自社株買いの実施や、連続増配の実績がある企業は、経営陣が株主価値を意識している証拠です。特に、10年以上連続で増配している企業(例:花王、KDDIなど)は、長期保有に非常に向いています。
これら5つの観点を総合的に分析することで、「安定 × 成長 × 株主還元」のバランスが取れた理想的な長期保有株を見つけることができます。
長期保有株ランキング【トップ10銘柄】
| 順位 | 銘柄(証券コード) | 業種・特徴 | 予想配当利回り(目安) | 連続増配(または直近の増配状況) |
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | メガバンク | 約 3.1%(会社予想) | 直近で増配(※複数期の増配実績あり) |
| 2 | 三菱HCキャピタル(8593) | リース・金融サービス | 約 3.7–4.4%(予想/報道) | 27期連続増配(メディア報道) |
| 3 | 日本郵船(9101) | 海運・物流 | 約 4.6%(会社予想) | 直近で増配(配当大幅引上げの経緯あり) |
| 4 | 日本たばこ産業(JT・2914) | たばこ・食品(ディフェンシブ) | 約 4.4–4.8%(予想・報道) | 2025年に増配を発表(高配当維持) |
| 5 | 伊藤忠商事(8001) | 総合商社(多角展開) | 約 2.2–2.3%(会社予想) | 安定配当・株主還元。増配は都度判断 |
| 6 | KDDI(9433) | 通信(生活インフラ) | 予想配当(会社目標):約 3%前後(配当額目標あり) | 20年超の連続増配(23期前後) |
| 7 | 花王(4452) | 日用品(生活必需) | 約 2.3–2.5%(予想) | 35〜36期連続増配(長期増配銘柄) |
| 8 | アサヒグループHD(2502) | 食品・飲料(海外展開) | 約 3.0–3.1%(予想) | 連続増配の実績あり(約9期などの報告あり) |
| 9 | 武田薬品工業(4502) | 医薬品(グローバル) | 約 4.7–4.8%(予想) | 近年は配当維持・増配は限定的(連続増配年数は短め) |
| 10 | INPEX(1605) | 資源・エネルギー(上流) | 約 3.5–4.4%(予想/報道) | 近年増配が続く(4〜5期連続増配の報道あり) |
この表は「安定×成長×株主還元」の3要素を軸に構成しています。
1位 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)
日本最大のメガバンクとして、安定した利益基盤を持つ三菱UFJフィナンシャル・グループは、約3.1%の予想配当利回りを維持しています。近年は収益改善を背景に複数期にわたる増配を実施しており、金融セクターの中でも長期保有向きの代表格といえます。
2位 三菱HCキャピタル(8593)
リース・金融サービスを手がける三菱HCキャピタルは、27期連続増配という国内有数の実績を誇ります。予想配当利回りは3.7~4.4%と高水準で、安定したキャッシュフローが強み。長期保有によるインカムゲインを狙う投資家に人気があります。
3位 日本郵船(9101)
海運業界の大手である日本郵船は、世界的な物流需要の高まりを背景に業績を拡大。予想配当利回りは約4.6%と高く、近年は配当を大幅に引き上げる動きも見られます。業績変動の大きい海運業の中でも、財務体質が堅実な点が評価されています。
4位 日本たばこ産業(JT・2914)
ディフェンシブ銘柄の代表格であるJTは、食品・医薬など多角化を進めつつ、海外事業の比率を拡大しています。配当利回りは約4.4~4.8%と高水準で、2025年にはさらなる増配を発表。安定したキャッシュフローを持ち、長期保有に向く高配当銘柄です。
5位 伊藤忠商事(8001)
商社業界で圧倒的な収益力を誇る伊藤忠商事は、安定配当を続けながら株主還元に積極的です。予想配当利回りは2.2~2.3%とやや低めですが、成長力と資本効率の高さが魅力。長期的に保有することで株価上昇と配当の両面からリターンを狙えます。
6位 KDDI(9433)
通信大手のKDDIは、生活インフラとして安定した収益を確保しており、20年以上の連続増配を記録。予想配当利回りは約3%前後で、安定的なキャッシュフローが特徴です。長期保有により、安定した配当と中期的な株価成長が期待できます。
7位 花王(4452)
日用品大手の花王は、35年以上連続増配という日本最長クラスの実績を持ちます。配当利回りは2.3~2.5%程度で、堅実な経営姿勢と高いブランド力が特徴。景気変動に強く、保守的な投資家にも人気の長期保有向け銘柄です。
8位 アサヒグループホールディングス(2502)
食品・飲料分野で国内外に展開するアサヒは、約3.0~3.1%の配当利回りを維持。9期前後の連続増配実績があり、グローバル展開による収益安定が強みです。消費関連セクターの中でも、安定感と成長性の両立が期待できます。
9位 武田薬品工業(4502)
グローバル製薬企業の武田薬品は、配当利回りが約4.7~4.8%と高く、国際的な事業基盤を有しています。ここ数年は配当維持を中心としていますが、研究開発パイプラインの充実により将来的な成長余地も大きいと見られています。
10位 INPEX(1605)
エネルギー開発を手がけるINPEXは、原油・ガス価格の動向に左右されるものの、安定した資源収益を背景に4~5期連続増配を継続中。予想配当利回りは3.5~4.4%と高水準で、エネルギー価格上昇局面では高リターンが期待できます。
これらの10銘柄は、いずれも配当の継続性・増配実績・財務健全性が評価されています。特に三菱HCキャピタル、KDDI、花王のように20年以上の増配を続ける企業は、インカムゲイン投資の王道といえます。一方で、伊藤忠商事やINPEXのような成長+配当の両立銘柄も、長期リターンを狙う上で魅力的な選択肢です。
長期投資を成功させるためのポイント

長期投資は「時間を味方につける投資法」と言われますが、ただ持ち続けるだけでは十分な成果は得られません。安定したリターンを得るためには、複利の力を最大限に活かしつつ、リスクをコントロールする戦略的な姿勢が求められます。
複利の力を活かす「配当再投資」
長期投資の最大の魅力は、配当を再投資することで生まれる複利効果です。受け取った配当金をそのまま消費せず、同じ銘柄や他の優良株に再投資することで、配当額と元本の両方が時間とともに増加していきます。
この「配当の雪だるま効果」は、10年・20年というスパンで大きな資産成長を生み出す原動力となります。
一時的な下落に動じない「長期メンタル」
どんな優良株でも、短期的には株価が上下します。長期投資では、この一時的な下落に動じないメンタルが非常に重要です。
企業の本質的な価値(ファンダメンタルズ)が変わっていない限り、価格の一時的な下落はむしろ買い増しの好機となることがあります。日々の値動きよりも、年単位での成長を見据える姿勢が、長期保有の成否を分けます。
定期的な「企業体力チェック」
保有銘柄の財務健全性や成長力を維持するためには、四半期ごとの業績発表の確認が欠かせません。特に、営業利益の推移、自己資本比率、フリーキャッシュフローの動向をチェックすることで、企業の体力や配当の持続性を把握できます。
長期保有中でも「決算内容に異変がないか」を見極めることが、損失回避の第一歩です。
税制優遇制度(新NISA)の活用
日本では2024年から「新NISA制度」がスタートし、非課税での長期運用がより容易になりました。配当や譲渡益にかかる税金を抑えられるため、長期保有株との相性は抜群です。
高配当・連続増配銘柄をNISA枠で保有すれば、税引後のリターンを最大化できます。
リスクを抑えるための注意点
経営方針や業界構造の変化
どれほど安定した企業でも、経営戦略の転換や業界構造の変化によって、長期的な成長が鈍化するリスクは存在します。
たとえば、通信業界では新技術や競争激化、エネルギー業界では資源価格の急変動が起こり得ます。こうした構造的リスクを認識し、定期的にポートフォリオを見直す姿勢が重要です。
「高配当=安心」ではない
高配当銘柄の中には、一時的な利益をもとに配当を支払っている企業もあります。したがって、配当性向(利益に対する配当の割合)が高すぎる場合は注意が必要です。
健全な配当を維持するには、企業が安定的にキャッシュを生み出しているかどうか、つまり営業キャッシュフローの強さを確認することが欠かせません。
分散投資でリスクを平準化
1つの銘柄に資金を集中させると、業界特有のリスクを避けられません。したがって、5〜10銘柄程度に分散投資するのが理想です。
たとえば、金融・通信・日用品・エネルギーといった異なるセクターに分散することで、特定の業種が不調でもポートフォリオ全体の安定性を保つことができます。
よくある質問(FAQ)
Q1.長期保有株はどのくらいの期間持ち続けるのが理想ですか?
一般的には5年以上の保有を目安とするのが理想です。
企業の成長や増配の効果が実感できるまでには時間がかかるため、少なくとも中長期での視点が必要です。特に複利効果を活かすためには、10年単位の運用が望ましいとされています。
Q2.高配当銘柄と連続増配銘柄、どちらを優先すべきですか?
目的によって選び方が異なります。
安定した配当収入を重視するなら高配当銘柄(例:JT・武田薬品工業)
将来の成長と増配を重視するなら連続増配銘柄(例:花王・KDDI・三菱HCキャピタル)
が向いています。両タイプを組み合わせてバランスを取るのが最も効果的です。
Q3.長期保有中に株価が下落した場合はどうすればいいですか?
まずは慌てて売らないことが大切です。株価が下落しても、企業の業績や配当方針に変化がなければ、長期的に持ち続ける価値があります。
ただし、業績悪化や減配が発表された場合は、保有方針を見直す判断が必要です。定期的に決算内容を確認し、企業の「本質的な強さ」を見極めましょう。
Q4.長期保有株はNISAで買った方がいいですか?
はい。新NISAは長期投資と非常に相性が良い制度です。
配当金や売却益に税金がかからないため、再投資効率が高まり、資産の成長スピードが大きく向上します。特に高配当株を非課税枠で運用すれば、複利効果を最大限に活かせます。
Q5.長期保有に向かない株はありますか?
業績が不安定で、配当の継続性が低い銘柄は長期保有に不向きです。
たとえば、景気や資源価格に大きく左右される企業や、配当性向が高すぎる企業は注意が必要です。安定的なキャッシュフローを維持できるかどうかが、長期投資における重要な判断基準となります。
Q6.長期投資のリターンを高めるコツはありますか?
最大のコツは配当再投資と分散投資です。
得られた配当を再び投資に回すことで、複利効果が働き、10年後・20年後のリターンが大きく変わります。また、業種や地域を分散することで、リスクを抑えながら安定的な収益を狙うことができます。
Q7.どのタイミングで買うのが良いですか?
長期投資では、完璧な買い時を狙うよりも「時間を味方につけること」が重要です。
相場が下落しているときや、企業の業績が一時的に落ち込んで割安になっているときはチャンスといえます。ドルコスト平均法(定期的な積立投資)を利用すれば、購入タイミングのリスクを減らせます。
結論:長期保有株で安定した資産形成を
長期投資の最大の強みは、「時間を味方にできる」ことです。短期的な値動きに左右されず、企業の成長とともに資産を育てていく姿勢が重要になります。
今回紹介したランキング銘柄のように、安定した収益基盤と増配実績を持つ企業を選び、配当を再投資しながら長期で保有することが、着実な資産形成につながります。
投資家それぞれのリスク許容度や目的に合わせて、自分に合った「長期保有株ポートフォリオ」を構築し、将来にわたって安定したリターンを得ることを目指しましょう。
免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。