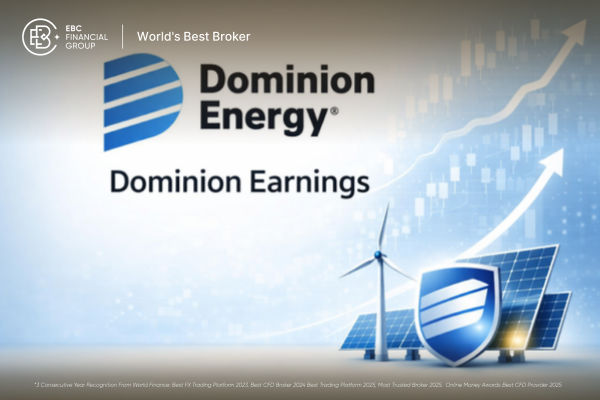取引
EBCについて
公開日: 2025-11-20
近年、日本では賃上げが広がり、物価上昇に伴って国内の消費が徐々に回復しています。さらに、円安の影響で外需企業は収益が振れやすくなる一方、国内市場を中心に安定して売上を上げる「内需関連株」への注目が高まっています。本記事では、こうした背景を踏まえ、今注目すべき内需関連株ランキングを紹介し、どのように投資判断に活かすべきかをわかりやすく整理していきます。
内需関連株とは?

内需関連株とは、日本国内の消費やサービス需要によって売上の大部分が成り立つ企業の株を指します。たとえば、スーパー・ドラッグストアなどの小売、レストランなどの外食産業、住宅や不動産関連、通信会社、電力・ガスといったインフラ企業、さらには医療・介護サービスや生活必需品メーカーなどが代表的な例です。これらの企業は、主に日本国内の消費者を対象としているため、海外の景気や為替変動の影響を受けにくいという特徴があります。
そのため、円安が続く局面や世界経済が不安定な時期でも、比較的安定した業績を維持しやすい点が魅力です。また、生活に欠かせないサービスや商品を提供する企業が多いため、景気が悪化しても需要が大きく落ち込みにくい「ディフェンシブ性」を持っています。投資初心者にとっても、企業のビジネスモデルがイメージしやすく、比較的リスクを抑えた投資がしやすいカテゴリと言えます。
内需関連株ランキングの選定基準
① 売上の国内比率
企業の売上のどれくらいを国内市場が占めているかは、内需株としての重要な指標です。国内比率が高いほど、円安の影響や海外景気の変動に左右されにくく、日本の消費動向を直接反映します。安定した国内需要を確保している企業ほど、内需関連株の中心的存在になります。
② 業績の安定性(営業利益率・売上成長率)
内需株は「安定感」が魅力のため、業績が長期的に安定しているかを重視します。具体的には、営業利益率が継続的に確保されているか、売上が過去数年にわたり緩やかでも成長しているかをチェックします。不況期でも利益を守れる企業は、長期投資でも安心感があります。
③ 株価モメンタム
直近の株価トレンドも重要な評価軸です。出来高の増加、移動平均線の位置関係、マーケット全体との相対的な強さなどを確認し、市場から買われている銘柄かどうかを判断します。勢いがある銘柄は、業績期待やテーマ性が市場と合致しているケースが多く、短期〜中期でも注目されます。
④ 配当利回り・株主還元姿勢
内需関連株には高配当銘柄も多く、株主還元の積極性は投資魅力を大きく高めます。安定したキャッシュフローを持つ企業は、長期的に配当を維持・増配しやすいため、長期保有の安心材料になります。配当だけでなく、自社株買いの有無もチェックポイントです。
⑤ 市場シェア・ブランド力
ブランド力があり、国内市場で高いシェアを維持している企業は、景気変動があっても一定の売上を確保しやすい特徴があります。競争優位性が明確な企業は、価格転嫁もしやすく、インフレ局面でも収益を維持しやすい強さがあります。
⑥ 景気敏感度の低さ(ディフェンシブ性)
内需関連株の中でも、景気の影響を受けにくいかどうかは重要です。食品、通信、医療、生活必需品などは、景気後退期でも需要が大きく落ち込まないため、株価の下落耐性が高い傾向があります。投資リスクを下げたいときに重視される基準です。
内需関連株ランキングトップ10(時価総額順)
| 順位 | 銘柄名(証券コード/業種) | 株価(円 | 時価総額(億円) |
| 1 | 三井住友フィナンシャルグループ(8316/銀行・金融) | 4,435 | 16兆7,000~17兆1,000 |
| 2 | 第一生命ホールディングス(8750/銀行・保険系) | 1,253 | 4兆6,300 |
| 3 | 野村総合研究所(4307/情報・通信) | 6,055 | 3兆5,000前後 |
| 4 | 清水建設(1803/建設業) | 2,485 | 1兆7,810 |
| 5 | ニトリホールディングス(9843/家具・インテリア) | 2,615 | 1兆4,963 |
| 6 | 三越伊勢丹ホールディングス(3099/小売・百貨店) | 2,357 | 8,661.70 |
| 7 | 丸井グループ(8252/小売・サービス) | 3,070 | 5,638 |
| 8 | 高島屋(8233/百貨店・小売) | 1,732 | 5,466 |
| 9 | 安藤・間(1719/建設) | 1,779 | 2,834 |
| 10 | ギフティ(4449/情報・通信) | 1,084 | 322 |
1.三井住友フィナンシャルグループ(8316:銀行・金融)
時価総額:約 16兆7.000~17兆1.000億円
株価:約 4.435円
この銘柄は国内向け金融サービスを主力とし、内需型金融企業としてアナリストの注目を集めています。
2.第一生命ホールディングス(8750:銀行・保険系)
時価総額:約 4兆6.300億円
株価:約 1.253円
国内の保険・金融サービスを中核とし、内需金融の一角として期待されています。
3.野村総合研究所(4307:情報・通信)
時価総額:約3兆5.000億円前後)
株価:約 6.055円
国内企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)やIT投資を通じて、内需情報サービスとしての成長力に注目されています。
4.清水建設(1803:建設業)
時価総額:約 1兆7.810億円
株価:約 2.485円
清水建設は大手ゼネコンの一角で、主に建築・土木・インフラ開発を手がけています。民間建築(オフィス・商業施設・住宅)を中心に、公共施設やインフラ、さらに環境・エネルギー系の事業にも力を入れており、内需の建設需要を幅広く取り込むビジネスモデルを持っています。
5.ニトリホールディングス(9843:家具・インテリア)
時価総額:約 1兆4.963億円
株価:約 2.615円
ニトリは国内家具・住宅需要に深く結びついており、自社ブランドの家具・インテリア製品で強い競争力を持っています。
6.三越伊勢丹ホールディングス(3099:小売/百貨店)
時価総額:約 8.661.7億円
株価:約 2.357円
三越伊勢丹ホールディングスは、三越・伊勢丹を中心とする百貨店事業を中核とし、加えてクレジット・金融、不動産、旅行、美容など多角的な事業を展開しています。
7.丸井グループ(8252:小売/サービス)
時価総額:約5.638億円
株価:約 3.070円
丸井グループは百貨系の小売・ショッピングセンター運営を手がけ、自社カード「エポスカード」による利益も大きな収益源となっています。
8.高島屋(8233:百貨店/小売)
時価総額:約 5.466億円
株価:約 1.732円
老舗百貨店として国内消費を取り込む力があり、インバウンド回復や高価格帯商品の需要もテーマとなり得ます。
9.安藤・間(1719:建設)
時価総額:約 2.834億円
株価:約 1.779円
中堅ゼネコンとして、住宅やインフラ向け建設を通じて内需の恩恵を受けやすい企業です。
10.ギフティ(4449:情報・通信)
時価総額:約 322億円
株価:約 1.084円
ギフティは、電子チケット/e‑ギフトの発行・流通を手がける企業で、個人・法人・自治体向けに多様なギフトサービスを展開しています。
注目テーマ別:強い内需関連株
1.賃上げメリット銘柄
賃金が上昇すると、消費者の購買力が高まり、売上が増加しやすい企業です。特に、日用品や食品、生活必需品を扱う企業は恩恵を受けやすく、景気の拡張局面では売上の伸びが加速する可能性があります。代表例としては、スーパーやドラッグストア、外食チェーンなどが挙げられます。
2.インバウンド依存度が低い国内純粋消費銘柄
外国人観光客(インバウンド)に依存せず、国内消費だけで安定した需要を持つ企業です。百貨店や食品メーカー、日用品メーカーなどが該当し、インバウンドの変動リスクを受けにくいため、安定した売上基盤を持つことが特徴です。
3.高配当+安定業績のディフェンシブ銘柄
業績が安定しており、配当利回りが高い企業です。景気の変動に左右されにくい内需型の公益事業(電力・ガス)、金融、食品などが代表的で、株価の下落リスクを抑えつつ、配当収入も期待できることから、長期投資家に人気があります。
4.DXや省人化で成長する小売・外食関連銘柄
デジタル化(DX)や省人化によって効率化・利益率向上を実現する小売・外食企業です。セルフレジやオンライン注文、無人店舗などの取り組みにより、売上や利益の拡大が見込めます。業界の成長テーマを取り込むことで、従来型の小売・外食業よりも高い成長性が期待されます。
内需関連株の投資戦略
1.分散投資の重要性(食品+通信+小売など)
内需関連株のリスクを抑えるためには、特定の業種に偏らず、複数のセクターに分散して投資することが有効です。例えば、食品・生活必需品、通信、百貨店・小売、建設など、内需消費やサービスに関連する異なる業種に分散することで、景気変動や業種特有のリスクに対してポートフォリオ全体の安定性を高めることができます。
2.長期投資で安定収益を狙うスタンス
内需関連株は、安定した国内消費やサービス需要を背景に、長期的な成長や安定収益を見込める銘柄が多くあります。短期的な株価変動に左右されず、配当や業績の着実な成長を重視して、数年単位で保有する長期投資スタンスが効果的です。
3.円安局面での優位性
内需型企業は、輸入コストや原材料費に敏感な製造業とは異なり、国内市場主体で収益を上げるため、円安局面でも比較的影響を受けにくい傾向があります。国内消費需要の強さを背景に、円安でも利益安定性が期待できる点が魅力です。
4.景気後退局面での防御力
生活必需品や公共サービスなど、景気の影響を受けにくい内需関連株は、景気後退局面でも比較的安定した収益を維持できます。ディフェンシブ銘柄としてポートフォリオに組み込むことで、景気変動による損失リスクを低減できます。
5.チャートで確認すべきポイント(移動平均、出来高など)
投資タイミングを見極める上では、株価チャートの基本的な指標を確認することが重要です。具体的には、短期・中期移動平均線のトレンド、出来高の増減、支持線・抵抗線の確認などを行い、上昇トレンドの確認や押し目買いのタイミングを判断します。これにより、長期投資での安定収益を狙う際のリスク管理が可能になります。
よくある質問(FAQ)
Q1.内需関連株はどんな相場で強い?
内需関連株は、国内消費やサービス需要に依存する企業の株です。そのため、景気拡大局面では個人消費や企業向けサービスの需要が増えるため、売上・利益ともに伸びやすく、株価が堅調になる傾向があります。また、円高・円安の影響を受けにくい銘柄も多く、国内市場主体の安定感が強みです。
Q2.景気悪化時でも買いなのか?
内需関連株の中には、生活必需品、電力・ガス、医療関連など、景気後退局面でも需要が大きく減らない銘柄があります。こうしたディフェンシブ銘柄は、景気が悪化しても比較的安定した収益を維持できるため、下落リスクを抑えつつ投資可能です。ただし、外食や百貨店など景気に敏感な内需株は注意が必要です。
Q3.高配当の内需銘柄は?
内需関連株の中でも、電力・ガス、銀行、食品メーカーなどは安定した利益を背景に、高い配当利回りを提供する銘柄が多くあります。長期保有による配当収入を重視する投資家に向いており、株価変動リスクを抑えつつ定期的なリターンを期待できます。
Q4.外需株との違いは?
外需株は、輸出や海外市場に依存する企業の株で、為替変動や海外景気の影響を受けやすい特徴があります。対して内需株は、国内消費やサービス市場を主な収益源とするため、為替の影響が小さく、国内経済の安定性に左右される傾向があります。投資目的やリスク許容度に応じて使い分けることが重要です。
Q5.長期保有に向いている内需株の条件は?
長期保有向きの内需株は、安定した利益基盤、持続的な成長力、そして配当政策が整っている銘柄です。生活必需品、電力・ガス、通信、住宅・建設など、国内市場で継続的な需要が見込める業種は特に長期投資に適しています。また、財務が健全で、景気変動時にも耐えられる企業を選ぶことが重要です。
結論
内需関連株は、国内消費やサービス需要に支えられた安定性の高い日本株の中心的なセクターです。投資では、食品や小売、建設、通信など複数業種に分散して保有することで、リスクを抑えつつ長期的な成長やリターンを狙えます。また、内需関連株ランキングや注目銘柄は市場環境や経済状況によって変動するため、定期的にポートフォリオを見直すことが重要です。
免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。