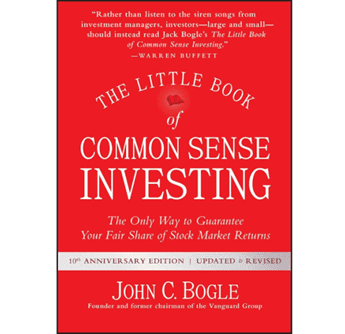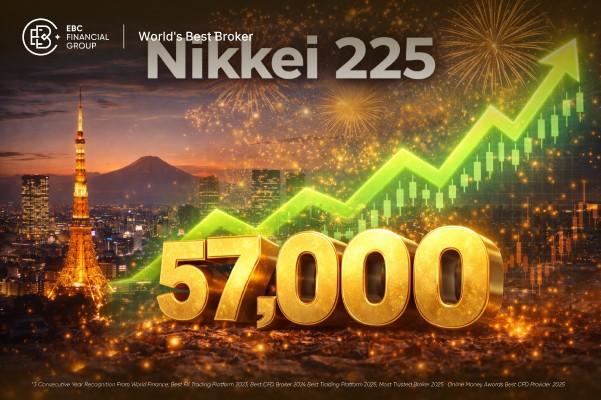取引
EBCについて
公開日: 2025-11-11
自動車業界は今、EV(電気自動車)シフトやAI・自動運転技術の発展など、大きな変革期を迎えています。ホンダもこの波に乗り、電動化への投資を加速させており、業界内での存在感が再び高まっています。
また、円安による輸出企業の業績押し上げや、原材料コストの落ち着きも株価にプラス要因となっています。こうした環境の変化を背景に、投資家の間では「ホンダ株を買うべきか」という関心が再び強まっています。
企業概要と事業構造

ホンダ(本田技研工業株式会社)は、日本を代表する総合輸送機器メーカーであり、自動車・二輪車・パワープロダクツの3分野を柱とするグローバル企業です。創業は1948年で、現在では世界60か国以上で生産・販売を展開しています。
主力事業のひとつである自動車部門では、「フィット」「シビック」「ヴェゼル」などの人気モデルを展開し、北米・アジア市場を中心に堅調な販売を維持しています。次に、ホンダの原点でもある二輪部門は、東南アジアを中心に圧倒的なシェアを誇り、世界最大の二輪メーカーとして知られています。さらに、発電機・芝刈り機・船外機などを扱うパワープロダクツ部門も、安定した収益源としてグループ全体の業績を支えています。
また、ホンダは売上の約8割を海外で稼いでおり、海外売上比率は非常に高いことが特徴です。特にドルやユーロなどの為替変動が業績に大きく影響するため、為替感応度は重要な投資判断材料となります。円安が進行すれば海外収益が増加し、逆に円高局面では利益が圧迫される傾向があります。
ホンダは多角的な事業展開と高い海外依存度を持つ、グローバル志向の企業といえます。
業績動向と財務状況
1. 売上高・営業利益の推移(過去数年)
2021 年度:売上高 約 13.17 兆円。
2022 年度:売上高 約 14.55 兆円と前年から増加。
2023 年度:売上高 約 16.91 兆円。
2024 年度:売上高 約 20.43 兆円、営業利益 約 1 兆3.819.8 億円、営業利益率 約6.8%。
2025 年度(2025/3期):売上高 約 21.69 兆円(前年比+6.2%)と増加、しかし営業利益は前年度の1.381.977 百万円から1.213.486 百万円へ減少(-12.2%)。
利益(親会社帰属当期利益)も2024 年度・2025 年度で1.107.174 百万円 → 835.837 百万円と約23.6%減少。
売上高は拡大傾向にありますが、直近では利益の伸び悩みや減少も見られ、営業効率やコスト・外部環境の影響が出ていると読み取れます。
2. EV・ハイブリッド車の販売動向
ホンダはハイブリッド車(HEV)を強化しており、たとえば「貢献して四半期利益最高を記録」という報道もあります。
ただし、全体として「EV(電気自動車)」市場での成長期待には慎重な姿勢が出てきています。業界的にはEV普及加速が鍵ですが、ホンダは “HEV重視” の戦略も示しています。
とは言え、具体的な数ユニットのEV/HEV販売台数が明確に公開されている統計資料は少なく、この点は「成長ポテンシャル」として注視すべきですが、リスクとしても捉えることができます。
3. 財務健全性(自己資本比率・フリーキャッシュフローなど)
負債比率・資本構成を見ると、たとえば「負債/資本(Debt to Capital Ratio)」は2024 年度末で約0.32(=長期負債/(長期負債+株主資本))と比較的低めの水準です。
負債/株主資本(Debt to Equity Ratio)もおおよそ0.36〜0.38程度で、同社や業界の中では“過度なレバレッジ”というにはやや余裕ありという評価もあります。
流動比率・運転資本の状況も、直近第4四半期で「運転資本比率=1.43倍」というデータが出ています。
キャッシュフロー面では、「研究開発費調整後オペレーティングキャッシュフローを年間で約3 兆円規模に改善」という報告があります。
ただし、単年度で利益が大きく減少しているため、利益率改善・キャッシュ創出の継続性には慎重な視線も必要です。
配当・株主還元方針
ホンダは株主への利益還元を経営の重要な柱のひとつと位置づけており、「安定・継続的な配当を支払う」ことを配当政策の基本としています。具体的には、連結配当性向(親会社帰属当期利益に対する配当金総額の比率)を概ね30%とすることを目安としています。
さらに、2026年3月期以降は配当政策指標として「DOE(自己資本に対する配当の割合:Dividends on Equity)」を導入し、目標値を概ね3.0%とすることを表明しています。
また、株主還元策として自社株買い(自社株式の取得)も積極的に行っています。たとえば、2025年までに最大11億株(※発行済株式数の約2割超)を上限とする自社株買いプログラムを承認しており、2025年5月時点でも数千万株を取得した実績があります。
このような自社株買いを通じて、資本効率の改善および1株当たり利益(EPS)などの株主還元価値の向上を図る姿勢が明確です。
配当利回りは国内株(東証:7267)でおおよそ4.5%程度とされ、過去10年にわたって増配傾向を維持しているとするデータもあります。ただし、直近では業績の影響で利益が減少している年もあり、将来の増配や利回り維持には外部環境や為替・コスト等の影響を踏まえた慎重な見方も必要です。
以上をまとめると、ホンダの株主還元方針は「(1)連結配当性向30%程度を目安とした安定配当」「(2)2026年度以降DOE3.0%を目安とした長期視点での配当維持」「(3)大規模な自社株買いによる株主価値向上」の三本柱で構成されており、長期投資家から見れば「配当+株主還元(自社株買い)によるリターン」が期待できる魅力的な側面があります。
とはいえ、リスクとしてはホンダが直面する構造転換期(EV化・為替変動・原材料価格上昇など)の中で、利益が揺らぎやすいという点があり、配当・株主還元施策の継続性を見極める必要があります。
株価動向と投資判断

① 現在の株価水準と PER・PBR の比較
株価水準として、直近の終値が「約 ¥1.585」程度であるとのデータがあります。
PER(株価収益率;Price Earnings Ratio)について、マーケットスクリーナー資料では“8〜10倍台”の水準が提示されています。たとえば「P/E ratio 8.72×」など。
PBR(株価純資産倍率;Price Book‐value Ratio)については、かなり低水準で「0.5倍台」あるいは「0.6倍前後」というデータがあります。例:「P/B ratio as of Nov 2025 : 0.4776」など。
ホンダ自身も「株価の評価がPBR1倍を下回っている状態」であることを報告し、経営側もこの低評価を重視している旨を述べています。
解釈:
ホンダは収益に対して株価が比較的安い(PERが低い)だけでなく、株主資本(帳簿上の純資産)に対しても市場評価が低く、PBRが1倍を下回る状態にあります。これは「割安」と評価される余地がある一方で、「なぜこの評価しかされていないのか=リスクが織り込まれている可能性」があることを示唆しています。
② アナリスト予想との乖離
アナリストの12か月先目標株価について、複数の情報があります。たとえば、TipRanksでは平均目標株価が「¥1.769.52」とされ、「現在株価から20%程度の上昇余地あり」との見方。
また、Marketscreenerでは平均目標株価が「¥1.744.38」、最高が「¥2.000」近くというデータも。
一方で、最近のアナリスト評価では慎重なコメントも増えており、たとえば「Macquarie銀行がホンダを「Neutral(中立)」に格下げし、目標株価を¥1.400に設定」というニュースも出ています。
解釈:
アナリスト予想は「現在価格から一定の上振れ余地あり」とするものが多いですが、同時に収益の先行き不透明感や構造転換期にある業界環境を反映して、慎重姿勢のものも目立ちます。つまり、「割安感+上昇余地あり」と捉えつつも「リスク要因も折り込み始めている」と言えます。
③ 中長期で見た買いタイミングの考察
買いタイミングを考える上でのポイント:
考察一:割安指標(低PBR・低PER)から「市場の期待を下回っている可能性」があり、中長期(数年単位)で成長方向が見えるなら魅力的です。
考察二:ただし、ホンダは現在、自動車産業のEV化・ハイブリッド化・自動運転化といった大きな構造変革の中にあります。これがスムーズに進むか否か、コスト・為替・素材価格・地域競争などのリスクが多くあります。
考察三:投資タイミングとしては、次のような状況を「買いの転換点」として考えても良いでしょう。
業績改善の明確な兆し(利益回復・収益性改善)
成長戦略(EV/HEV、自動運転等)で実績が出始めること
株価が直近の下値支持線付近で反発の兆しがあること。テクニカル指標では「約 ¥1.589」あたりに支持帯があるという指摘も。
現在の考え方:
ホンダ株を買うべきかを判断するなら、やや早期とも言え、中長期(3〜5年程度)保有を前提に、「割安+成長転換への期待」が見える点を重視しておくべきだと思われます。逆に、短期(1年以内)だけを見て買うなら、業績や戦略実行の遅れ・リスクが株価に織り込まれる可能性を考慮し、慎重な姿勢が求められます。
リスク要因
ホンダ株を検討する上で重要なリスク要因を、具体的な内容・影響の仕方・投資家が注視すべき指標の順で整理します。
1) 為替変動リスク
内容と影響:ホンダは売上の大部分を海外で稼いでおり、ドルやユーロなどの外貨収益を円換算して計上します。円安は海外売上の円換算額を押し上げ利益増に寄与する一方、円高は利益を圧迫します。また、部品調達や設備投資で外貨建てコストが発生する場合、為替変動はコスト面でも影響します。
影響の出方:短期的には四半期決算の営業利益や当期純利益に直接反映され、株価のボラティリティを高めます。長期的には為替のトレンドが通期業績や配当余力へ波及。
投資家が見るべき指標:為替(USD/JPY、EUR/JPY)の推移、ホンダの為替感応度開示(為替1円変動での営業利益影響額)、四半期/通期の為替影響注記。ヘッジ方針の変更(為替ヘッジの有無や比率)も重要。
2) EV開発競争の激化(技術・コスト・市場競争)
内容と影響:自動車業界はEVへの移行が加速しており、技術力(電池・制御ソフト)、量産体制、価格競争力が勝敗を分けます。中国の地場EV勢やテスラ、トヨタなどライバル各社の投資・発売スピードが速い中で、ホンダの技術・製品投入の遅れは市場シェア喪失・販売価格の下落圧力につながります。
影響の出方:中長期的に新車販売構成比・マージンに直結します。電池コスト低下やサプライチェーン最適化で取り残されると、利益率悪化につながる可能性がある。
投資家が見るべき指標:EV/HEVの販売比率、主要市場(中国・米国・欧州)でのモデル発売スケジュール、EVに関するR&D費の推移、車両あたりの部材コスト(特に電池関連)、提携・サプライ契約の発表。プロダクトの受注状況や予約数の開示も重要。
3) 世界的な景気後退・金利動向の影響
内容と影響:自動車は景気循環に敏感な高額耐久消費財です。世界的な景気後退や高金利が続く局面では消費者の購買意欲が縮小し、新車需要が落ち込むリスクがあります。金利上昇は自動車ローン金利を押し上げ、需要抑制要因になります。さらに、景況感悪化は企業の設備投資やフリート購入にも影響します。
影響の出方:販売台数減→売上減少→在庫調整・値下げ圧力→利益率低下、という流れで中短期の業績悪化を招く可能性があります。加えて、信用コスト上昇や金融部門(販売金融)への負担も懸念される。
投資家が見るべき指標:世界/主要国のPMI、消費者信頼感、主要市場の自動車販売台数、中央銀行の政策金利動向、販売金融(カーリース・ローン)の不良率や与信状況。
4) サプライチェーン・原材料コストリスク
内容と影響:半導体、リチウム・ニッケルなど電池材料、鋼材やその他部材の供給制約や価格高騰は生産遅延・コスト増を招きます。特にEV化に伴うバッテリー原料の価格変動はコスト面で重大です。
影響の出方:期ズレによる納期遅延、コスト転嫁が難しい場合の利益圧迫、あるいは生産調整による売上減少。
投資家が見るべき指標:部材価格(主要コモディティ)、半導体供給状況、在庫回転率、生産稼働率、サプライヤー多様化の進捗。
5) 規制・環境・安全性リスク
内容と影響:各国の排出規制、補助金政策、リコールや安全基準の強化は製品戦略に影響します。特に厳格な排出基準や安全規制の導入は追加開発コストや販売戦略の見直しを余儀なくします。
影響の出方:コンプライアンス対応コスト、販売停止・リコール費用、ブランドイメージ低下による需要減。
投資家が見るべき指標:主要市場の排出規制・補助金の変更、リコール件数や関連費用、環境規制対応の進捗。
6) 経営・実行リスク(戦略の実行力)
内容と影響:長期目標(EV化や自動運転など)を掲げても、実行体制、資金配分、提携先との関係、社内の技術・人材確保が伴わなければ計画は達成できません。戦略の遅延・方針転換は市場の信頼低下を招きます。
影響の出方:期待先行の株価が戦略の後退で急落する、投資回収が遅れることでキャッシュフロー圧迫。
投資家が見るべき指標:中期経営計画の進捗報告、主要プロジェクトのマイルストーン達成度、経営陣の発言やガイダンス変更。
リスク管理の観点:投資家ができること
分散:単一銘柄比率を抑える。
シナリオ想定:為替変動やEV普及のスピード別に投資シナリオを作る。
トリガー条件設定:四半期業績や特定指標(為替、EV販売比率、R&D投資額など)が一定水準を下回ったら見直す、などの明確な売買ルールを持つ。
長短の投資方針を明確化:短期でのトレードか中長期の成長投資かで捉え方が変わる(短期はマクロ指標重視、中長期は戦略実行力と財務健全性重視)。
よくある質問
Q1:ホンダ株の今後の配当見通しは?
ホンダは安定したキャッシュフローを維持しており、株主還元にも積極的です。2025年度の予想配当利回りは約3%前後と見込まれ、業績に応じた柔軟な増配も検討されています。特に北米市場の好調や為替の追い風が続けば、さらなる増配の可能性もあります。
Q2:ホンダ株とトヨタ株、どちらが有望?
トヨタはEV・ハイブリッド車の技術力と市場シェアで優位に立つ一方、ホンダは四輪に加え二輪車や航空機などの多角化事業が強みです。短期的な成長性を重視するならトヨタ、事業の分散性と中長期的な成長ポテンシャルを重視するならホンダが有望と言えます。
Q3:ホンダのEV戦略は他社に比べて遅れている?
確かにホンダはEV市場参入でトヨタやテスラに遅れをとった面がありますが、近年は巻き返しを図っています。2026年以降には北米市場向けの新型EV「0シリーズ」を投入し、ソニーとの合弁会社「ソニー・ホンダモビリティ」を通じて次世代車開発を加速中です。さらに、固体電池の量産体制構築にも取り組んでおり、今後の進展が注目されています。
結論:ホンダ株を買うべきか?
ホンダ株は中長期的に成長が期待できる銘柄です。EVシフトや新技術への投資が進めば、収益拡大の可能性があります。ただし、短期的には円高や原材料コストの上昇など外部要因の影響を受けやすく、慎重なエントリーが求められます。今後はEV事業の進捗と利益の安定性が投資判断の重要なポイントとなります。
免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。