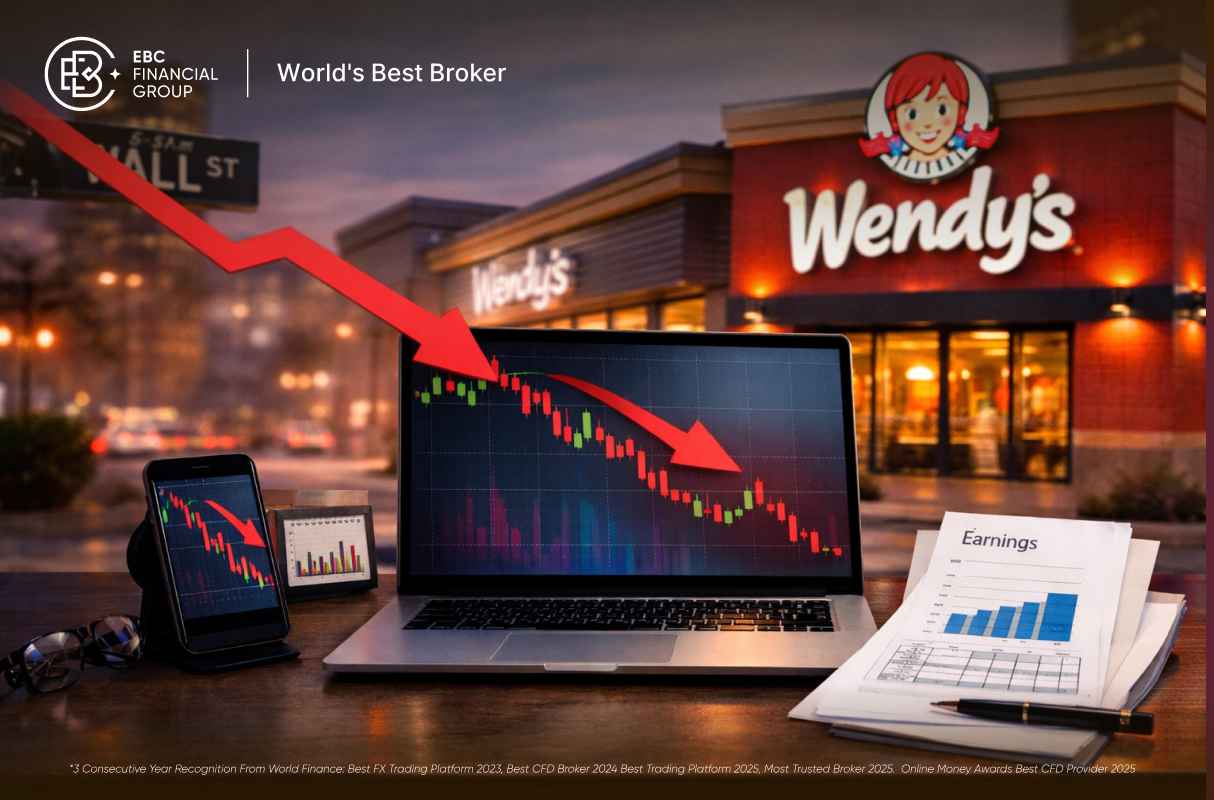取引
EBCについて
公開日: 2025-11-13
ニデック(旧日本電産)は、精密モーターの世界トップクラス企業として知られ、EV(電気自動車)やロボティクス、家電、自動化機器など幅広い分野で事業を展開しています。特に、EV用駆動モジュール「e-Axle」は次世代自動車産業の中核技術として注目され、国内外の大手自動車メーカーからも信頼を集めています。
しかし、こうした高い技術力と世界的な存在感にもかかわらず、近年のニデック株は思うように上昇していません。業績は堅調にも見える一方で、株価は横ばいもしくは下落傾向を示しており、市場評価とのギャップが広がっています。
そのため、投資家の間では「ニデック株価がなぜ上がらないのか?」という疑問が強まっています。本記事では、その背景にある要因を整理し、今後の成長可能性を多角的に検証します。
現状分析:ニデック株価の推移と市場の評価

1.株価の推移(ここ1〜3年)
株価は2025年11月12日時点で 約 2,285円。
年初来高値は 3.296円(2025年8月25日)で、年初来安値は 1,797円(2025年10月31日)となっています。
指標の一つとして、PBR(実績ベース)は 1.52倍前後。
PER(予想ベース)は公開データで“‐”(一部未公表)となっているものの、2025年3月期実績ベースでは54.90倍という記録があります。
過去3年を見ると、PBRが「約4倍→約2倍→約1.6倍」へと低下傾向にあります。
これらから、「株価がかつての高値から大きく下がっており、さらに株価指標的にも「割高」から「割安」?ないしは「評価が低まった水準」に移行している可能性」が読み取れます。
2. 市場の評価・株価指標・同業他社比較
PBRが約1.52倍というのは、資産価値(BPS)に対して株価がそれほど高く評価されていない水準とも言えます。
PERに関しては実績ベースで54.9倍(2025年3月期)という高めの水準も確認されています。
一方、アナリスト目線で算出された「理論株価(PBR基準)」が約2.671円という試算もあります。
株価が2.285円という状況で「理論株価2.671円」という数字が出てくることから、市場参加者の間には「評価・再上昇余地あり」という見方も出ています。
ただし、同業他社(例えば、安川電機、ファナック 等)との明確な指標比較は本資料では省略されています。が、精密部品・モーター分野という観点では、競合環境も評価に影響していると考えられます。
3.気になる点・停滞のサイン
年初来高値からの下落幅が大きく、特に2025年10月末時点で安値1.797円をつけており、株価の「勢い」が弱っている可能性があります。
PERが高いレンジ(54.9倍)を記録していたにも関わらず、現在の株価・PBR水準にまで低下しているということは、「将来の成長想定が株価に十分織り込まれていない/もしくは期待が剥がれた」可能性を示唆します。
また、直近で同社は2026年3月期の業績・配当予想を未定とするという発表があり、それを嫌気した売りが増加したという報道もあります。
市場参加者の間で「評価が低まっている」「成長シナリオに懐疑的」という雰囲気が見え隠れします。
ニデック株価がなぜ上がらないの?

(1)業績の成長鈍化・EV市場の減速
ニデックは「次世代モビリティ/EV(電気自動車)用モーター(e-Axle等)」に大きく賭けており、成長ドライバーと位置付けられてきました。
しかし、外部から「成長ペースが想定ほど速くない/足元で競争・市場環境が厳しい」との指摘があります。例えば、モーニングスターの記事では「EVトラクションモーター出荷想定を94.9万台から35万台に引き下げた」といった内容があり、成長期待が剥落しつつあるとの見方が紹介されています。
また、ロイター報道では「EV需要の鈍化」が株価停滞の一因として挙げられています。
加えて、ニデックの決算報告でも、自動車関連(Automotive Products)部門において既存事業が利益化段階に移行してきたものの、設備投資・構造改革コストを伴っており、利益率の改善が滑らかではないことが示されています。
こうした状況は「成長ストーリーが株価に十分織り込まれていない/市場期待に対して少し遅れている」可能性を示唆します。
(2)為替影響・海外依存の高さ
ニデックはグローバル展開しており、売上・利益ともに海外通貨建ての影響を受けやすい企業です。
決算資料によると、2024年度(3月期)では、円安(ドル・ユーロに対して)によるプラス効果として「売上に約1.007 億円、営業利益に約67 億円」の好影響があったと報じられています。
逆に言えば、円高局面や海外でのコスト増(例えば中国・欧州)などが影響を及ぼすリスクを抱えており、海外依存度が高い構造が株価にとって警戒材料になっています。
また、海外(特に欧州・中国市場)でのモーター部品やEV関連投資が景気・政策・競争によって変動しやすいため、「収益のブレが大きい/予測が立てづらい」という点も投資家からの評価を下げる要因です。
(3)投資負担と利益率低下
成長を見据えた設備投資・M&A・生産体制の再構築といった費用負担が、短期的には利益率低下要因になっています。 決算資料では、例えば「機械(Machinery)部門」で営業利益が前期比12.2%減少したと報じられています。
また「自動車(Automotive)部門」においては、売上は増加しているものの、まだ利益率の改善途上であり、構造改革中という文言も見られます。
こうした「成長のための先行投資 → 短期的な利益率低下/収益の先送り」が、株価上昇を抑える要因の一つとして働いていると考えられます。
(4)経営体制や市場期待のズレ
市場参加者からは「成長期待と実際の進捗のギャップ」が意識されており、たとえば欧州自動車市場の低迷や中国競争激化の中で、当初描かれていた“キャッチアップ”シナリオが少しリスク化してきています。
経営体制についても、過去の積極的なM&A戦略・拡張戦略から「これからの成長をどう描いていくか」という点が注目されており、明確なロードマップが市場にとってまだ安心材料とはなっていない可能性があります。
ポジティブ要因:ニデックの将来性と回復シナリオ
(1)EV・自動運転分野での潜在力
ニデックは次世代モビリティ領域、特に電気自動車(EV)用駆動モータシステム「e‑Axle」に注力しています。公式技術ページでは「当社のe-Axleは出力135 kW、トルク2.400 Nm、重量57 kg」という第二世代モデルを2022年10月から量産開始したとしています。
また、「EV大衆普及期」の始まりとなる2025年を「転換点(turning point)」と位置づけ、2030年までにEV新車販売において50%超となるという外部予測も挙げられています。
ニデック自身は2030年までに売上高10兆円を目標に掲げ、その内訳として「自律的成長による7兆円+M&A等による3兆円」などを公表しています。
こうしたことから、EV用モーターという成長ドメインでの技術優位・生産体制・市場機会という三拍子がそろっており、ニデックには「将来成長の柱」になり得る分野が存在します。
投資家視点で言えば、「EVの普及ペースが見込まれる」「モーター/駆動系という部品で世界的シェアを取る余地がある」「技術・生産で優位性がある」という期待材料になります。
(2)ロボット・産業機械モーターでの需要拡大
ニデックは「ロボット/自動化機械」向けモーター・ドライブモジュール技術にも強みがあります。たとえば「自動搬送ロボット(AGV/AMR)用ドライブモジュール」の事例として、物流倉庫に100台以上が稼働していると紹介されています。
さらに、ロボット・自動化市場では、中国をはじめとするアジア圏での需要が急拡大しており、例として「ニデックの子会社が中国のロボットブームを狙っている」といった報道もあります。
産業用ロボット・物流ロボット・自動化設備(省人化ニーズ)が世界的に強まっており、この流れはモーター・ドライブ制御が主役級の製品となるため、ニデックのようなモーター専業企業には追い風があると見られます。
このように、EV以外の成長ドメインとして「産業機械・ロボット関連」も重要であり、ニデックの中期戦略上でも「Productivity Efficiency(生産性効率化)」というキーワードが挙げられています。
(3)構造改革・収益改善の動き
ニデックは中期経営計画「Vision 2025」において、2025年までに売上4兆円、2030年に10兆円を目標と掲げています。
また、財務資料によると2024年度時点において営業利益率を9.1%から11%へ、ROIC(資本収益率)を7.1%から12%へ引き上げるという改善目標が出ています。
加えて、「One NIDEC(グループ統合経営)」をキーワードに、世界各地の子会社を統合・効率化し、高付加価値製品への転換・生産体制の見直しを図っていることが記されています。
これらの動きから、単に「成長分野に賭ける」だけでなく、コスト圧縮/収益性改善/構造改革という「質」の改善にも取り組んでおり、株価や市場評価が“成長期待+収益改善”という両方を捉えた時に再評価される余地があると考えられます。
投資判断:ニデック株は「買い」か?
A. 現在の株価水準と割安性の評価
株価水準:直近ではおおむね2.000〜2.400円帯で推移しており、年初来の高値(約3.296円)から大きく下落している局面です(短期でボラティリティが高い)。
指標:PBRは概ね1.3〜1.6倍、PER(会社や情報源により変動)が示すレンジもあり、アナリスト平均目標株価は約3.300〜3.600円と設定されているため、アナリストのコンセンサス上は現在に上昇余地があるとの見方が多いです。
要解釈点:ただし「理論的な割安感」はあくまで普通の業績想定が成り立つことが前提。現在はガバナンス問題や業績予想の白紙化などで不確実性が高く、市場はリスクプレミアムを大きく乗せた価格を付けています。
B. 長期目線での成長期待とリスクバランス
B1.ポジティブ要因(長期)
EV用モーター(e-Axle)やロボット用モーターなど、ニデックが強みを持つ成長市場は依然大きく、技術・生産力を背景に中長期での収益拡大ポテンシャルは残ります。多くのアナリストは中期でのリバウンドを想定しています。
B2.リスク(短中期で株価に致命的な影響を与えうる)
会計・ガバナンス不安:内部調査での不正会計示唆により2025年9月以降に大幅下落、外部独立委員会調査・監査未確定が続き、投資家心理が痛手を受けています。
取引所からの特別注意・指数からの除外リスク:東京証券取引所の“特別注記(改善命令)”や日経225からの除外といった事象は、インデックス連動売りを誘発し、需給面での下落圧力を強めます。実際に株価急落を招いた事例があります。
業績・配当の不確実性:監査の問題や決算の見直しで四半期・通期見通しが未定・白紙化されると、配当や自社株買いの継続性も疑問視され、投資魅力が薄れます(会社は本来は配当を継続方針だが、事情により一時停止の報道もあり)。
B3.結論(長期 vs 短期):
短期(~12ヶ月):ガバナンス・監査問題の解明が見えるまでは不透明感が強く、ボラティリティも高いです。短期トレードはリスクが高いです。
中長期(数年):もし独立調査で致命的な不正が否定され、監査意見も回復、かつEV/ロボ分野での収益改善が見えれば、再評価余地(上方余地)は大きいです。そのため中長期での価値投資候補になり得ますが、「復活の条件」がクリアになって初めて割安といえます。
C. 投資家への具体的アドバイス(行動プラン)
C1.短期投資家(デイト〜数ヶ月)
ガバナンス問題や取引所の評価(特別注記・上場維持リスク)で急落リスクが残るため、現状は回避が無難。やむを得ず関与する場合は厳格なストップロスを設定し、ポジションサイズを小さくします。
C2.中長期投資家(1年以上)
買いの条件(チェックリスト)を用意する:
独立第三者委員会の調査結果が公表され、重大な不正が否定されるか是正計画が提示されること。
監査法人(外部監査)の意見または再監査で合理的な説明が得られること。
決算の見通し(業績ガイダンス)や配当方針が正常化すること。
EV/ロボ分野での具体的な受注・量産化・マージン改善の進捗が確認できること。
上記が整った段階で、段階的に買い増す(ドルコスト平均法)のがリスク管理上有効。
C3.ポートフォリオ管理
個別リスクが高いため、個別株比率は慎重に(例:株式ポートフォリオの5%以下など)。
ニュースフロー(監査報告、第三者委員会の発表、取引所からの通告、業績開示)をリアルタイムで監視する体制を持つ。
よくある質問(FAQ)
Q1.ニデック株価がなぜ上がらないの?
会計監査の遅れやガバナンス問題への懸念が続き、投資家の信頼が回復していないためです。業績や技術は強みがあるものの、リスク要因が株価を抑えています。
Q2. 今後、株価は上がる可能性はありますか?
あります。監査問題が解決し、業績見通しや配当が正常化すれば、信頼回復による上昇が期待されます。特にEVモーター事業の進展が鍵となります。
Q3. 配当はどうなる?
現時点では一部停止・未定ですが、決算が正常化すれば再開の可能性があります。現金収支が安定すれば、株主還元方針も復帰する見通しです。
Q4. 今は買い時?
短期的にはリスクが高く「待ち」が無難です。監査報告や業績ガイダンスが明確になった段階でのエントリーが安全です。
結論
ニデック株価がなぜ上がらないかは、ガバナンス問題や会計監査の遅れなどの短期的要因に加え、EV市場への過度な期待が一時的に剥落したことが背景にあります。市場は依然として不信感を払拭できず、株価にはリスクプレミアムが反映されています。
しかし、ニデックの事業基盤は依然として強固であり、モーター技術やEV・ロボット関連の競争力は世界トップクラスです。これらの成長分野が再び軌道に乗れば、中長期的には再評価の可能性が十分にあると言えます。
つまり、現時点では慎重な姿勢が求められるものの、信頼回復と業績改善が進めば、ニデックは再び「成長銘柄」として市場に戻る潜在力を持っています。
免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。