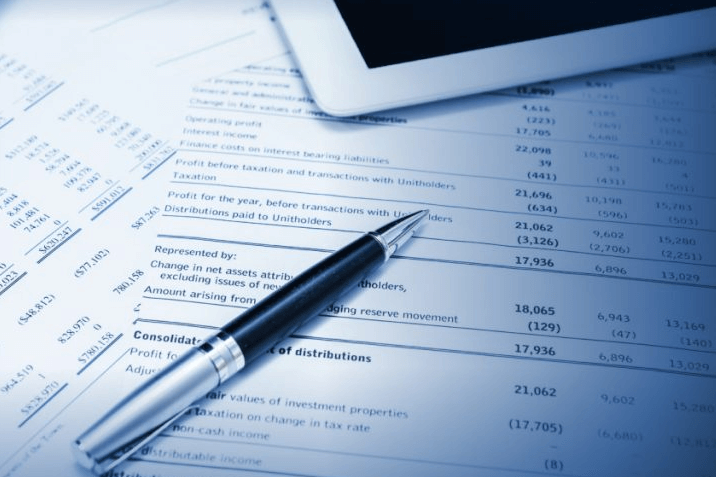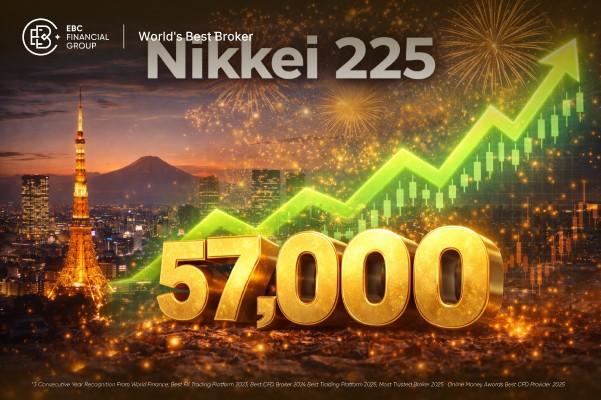取引
EBCについて
公開日: 2025-08-12
評価損益額とは、現在保有している資産がどれだけ利益や損失が出ているかを示す指標です。投資や資産運用を行ううえで、自分の資産の状況を把握するために非常に重要なものです。本記事では、評価損益額の意味や計算方法、そして投資判断にどう活かせるかについてわかりやすく解説します。これを理解することで、より賢く資産管理ができるようになります。
評価損益額とは何か

評価損益額の定義
評価損益額とは、現在保有している資産の時価(市場価格)とその取得価格の差額を指します。つまり、保有資産が今どれだけ利益を出しているのか、または損失が出ているのかを示す数値です。
たとえば、株を1000円で買って現在の価格が1200円なら、評価損益額は+200円となり利益が出ている状態を表します。
「評価」とは何か
「評価」とは、保有している資産の現在の市場価値を意味します。株式や投資信託、FXなどは市場で価格が変動するため、時点ごとに資産の価値を評価し直す必要があります。この「評価」があることで、資産の今の価値をリアルタイムで把握できます。
「損益」とは何か
「損益」とは、利益や損失のことです。評価損益額は、資産の現在価値と購入価格との差で計算されるため、プラスであれば利益(評価益)、マイナスであれば損失(評価損)となります。
実現損益との違い
評価損益額は「未実現損益」とも呼ばれ、あくまで保有している資産の現時点での理論上の利益や損失です。実際に資産を売却し利益や損失が確定するまでは、あくまで「評価」された状態に過ぎません。一方、売却などで損益が確定したものは「実現損益」と呼ばれます。投資判断を行う際は、この違いを理解しておくことが大切です。
評価損益額の計算方法
1.基本の計算式
評価損益額は、次のような計算式で求められます。
評価損益額 = 現在の時価評価額 - 取得原価
現在の時価評価額とは、保有している資産の現在の市場価格に保有数量をかけた金額です。
取得原価とは、その資産を購入したときの合計費用(購入価格×数量)を指します。
2.具体例を用いた計算例
例えば、ある株を100株、1株あたり1.000円で購入したとします。
取得原価は 1.000円 × 100株 = 100.000円
その後、株価が1.200円に上昇した場合、現在の時価評価額は
1.200円 × 100株 = 120.000円
このときの評価損益額は
120.000円 - 100.000円 = +20.000円(評価益)
逆に株価が800円に下落した場合は
800円 × 100株 = 80.000円
80.000円 - 100.000円 = -20.000円(評価損)
金融商品ごとの違い
評価損益額の計算自体は基本的にどの金融商品でも同じですが、対象によって次のようなポイントがあります。
株式・投資信託:保有数量×現在の価格で評価。分配金や配当金は別途考慮することもある。
FX(外国為替証拠金取引):ポジションの建玉数量×為替レートの差で評価。レバレッジの影響も受けやすい。
債券:利息収入と時価変動を分けて評価する場合がある。
コモディティ先物やその他デリバティブ:取引の仕組みにより計算方法が複雑になる場合もある。
それぞれの金融商品特性に応じて、評価損益額の見方や管理方法が変わるため注意が必要です。
なぜ評価損益額が重要なのか?
投資判断に役立つ理由
評価損益額とは、現在保有している資産がどれだけ利益を出しているのか、あるいは損失を抱えているのかをリアルタイムで示してくれるものです。これにより、投資家は自分の資産状況を正確に把握でき、今後の売買判断に役立てることが可能です。たとえば、評価損益額が大きなプラスなら利益確定を考える材料に、逆に大きなマイナスなら損切りの検討材料になります。
ポートフォリオの見直しに活用できる
複数の銘柄や資産を保有している場合、各資産の評価損益額を確認することで、全体のバランスを見直すことができます。評価損益額がプラスの資産に偏りすぎている場合はリスク分散のために一部を売却したり、逆にマイナスが続く資産の見直しを行ったりすることで、健全なポートフォリオ管理が可能になります。
損切りや利益確定のタイミング判断の参考に
評価損益額とは、損切り(損失を確定させる売却)や利益確定のタイミングを判断する際の重要な指標です。例えば、一定の損失額や利益額に達したら売却するといったルールを設けることで、感情的な取引を避け、計画的に資産を管理できます。この際、評価損益額が常に変動するため、こまめなチェックが必要です。
税務上の扱いと関連性(未実現損益としての位置づけ)
評価損益額はあくまで「未実現損益」であるため、売却や決済をしない限り税金は発生しません。つまり、評価損益額は税務上の損益とは異なり、確定申告や税金計算には影響しません。ただし、税務申告の際には実現損益を基に計算されるため、評価損益額はあくまで資産管理や投資判断のための参考値として利用されます。
評価損益額を活用した投資戦略のポイント
評価損益額だけにとらわれない重要性
評価損益額とは現在の資産の利益・損失状況を示す重要な指標ですが、これだけに過度に注目すると冷静な判断を欠くリスクがあります。例えば、一時的に大きな評価損が出ていても、長期的な成長を期待して保有を続けるケースもありますし、逆に評価益が出ているからといって即座に売却するのが必ずしも良いとは限りません。評価損益額はあくまで一つの目安として活用し、企業の業績や市場環境、将来性など多角的な視点を持つことが重要です。
1.長期保有と短期取引での見方の違い
投資スタイルによって、評価損益額の捉え方は変わります。
長期保有の場合
長期間の保有を前提としている場合、短期的な価格変動による評価損益額の増減はあまり気にしすぎず、企業のファンダメンタルズ(業績や成長性など)を重視します。評価損が出ていても一時的な市場の調整と捉え、資産の価値が回復するまで待つこともあります。
短期取引の場合
デイトレードやスイングトレードのような短期取引では、評価損益額の変動が売買タイミングの判断に直結します。利益が出ているうちに確定したり、損失を限定するために損切りを速やかに行うことが重要です。そのため、評価損益額の変動を頻繁にチェックし、素早く対応できることが求められます。
2.マーケットの変動に合わせた柔軟な判断
市場は常に変動しており、評価損益額も日々変わります。重要なのは、変動に過剰に反応せず、柔軟に対応することです。
短期的な急激な変動は一時的なものかもしれないため、慌てて売買するのではなく冷静に状況を見極めること。
市場全体の動向や経済指標、政治的要因なども考慮しながら評価損益額の状況を判断する。
必要に応じて投資方針の見直しやリバランスを行い、リスクを適切に管理する。
このように、評価損益額は投資戦略の重要な参考情報ですが、それだけに頼らず、総合的な判断材料として活用することが成功への鍵となります。
注意点・リスク
評価損益額とはあくまで「未実現」の損益であること
評価損益額は、資産をまだ売却していない状態での理論上の利益や損失を示しています。つまり、実際に利益や損失が確定しているわけではありません。そのため、市場価格が変動すれば評価損益額も日々変わるため、過信するのは危険です。評価損益額がマイナスでも、将来的に価格が戻れば損失はなくなることもありますし、逆にプラスでも価格が下落すれば利益が消えるリスクもあります。
市場価格の変動によって日々変わること
評価損益額は市場の動きに連動して変動します。株式市場や為替市場は短期間で大きく値動きすることがあり、評価損益額もそれに応じて上下します。特に相場が不安定なときは、評価損益額の変動が激しくなるため、毎日の数字に一喜一憂せず、長期的な視点を持つことが大切です。
精神的な影響(過剰な売買判断を避けるために)
評価損益額の変動は投資家の心理に大きな影響を与えます。短期間で大きな含み損が出ると不安になり、焦って損切りしてしまうことがあります。逆に、含み益が出ると過信して無計画に売買を繰り返すリスクもあります。こうした精神的な影響を受けると、冷静な判断が難しくなり、結果的に損失を拡大させることも。投資では、評価損益額に振り回されず、あらかじめ決めたルールや戦略に従うことが重要です。
結論
評価損益額とは、保有している資産の現在の利益や損失を把握するための大切な指標です。計算方法や意味を理解し、投資判断や資産管理に役立てることができます。ただし、評価損益額だけに頼らず、長期的な視点や他の情報も組み合わせて活用することが重要です。これを踏まえて、賢く資産運用を進めていきましょう。
免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。