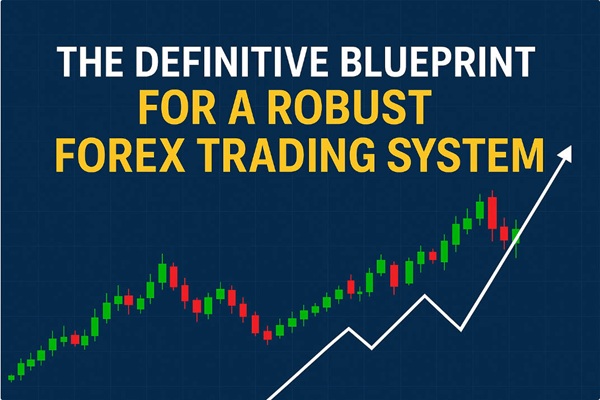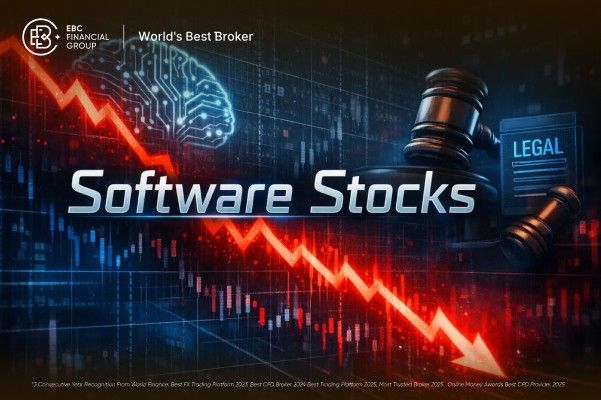取引
EBCについて
公開日: 2025-09-17
投資の世界では株式や債券の比率を決める「資産配分」が重視され、伝統的な60:40ポートフォリオが代表例として知られていますが、実際には株式の変動が大きいため資金割合が同じでもリスクは偏り、下落局面で損失が集中するという課題があります。こうした問題を克服する方法として注目されているのが「リスクパリティ戦略」で、これは資産を資金額ではなくリスク寄与度に基づいて配分し、より安定したリターンを追求する投資手法です。
リスクパリティ戦略とは

リスクパリティ戦略とは、株式や債券、コモディティなど複数の資産クラスに投資する際に、「資金の配分」ではなく「リスクの配分」を均等にすることを目的とした投資手法です。従来の資産配分(アセットアロケーション)は「株式に60%、債券に40%」のように投資金額の比率を基準にしてきましたが、この方法ではリスクの大半を株式が占めてしまう傾向があります。
リスクパリティ戦略では、各資産の値動きの大きさ(ボラティリティ)や相関関係を考慮し、ポートフォリオ全体に対する「リスク寄与度」を均等に調整します。例えば、株式はリスクが大きいため配分を抑え、逆に安定的な債券やコモディティにはレバレッジをかけて投資比率を高めるといった工夫が行われます。
この結果、特定の資産に偏らないバランスの取れたポートフォリオが構築され、市場環境の変化に強く、安定したリターンを目指すことが可能となります。
リスクパリティの仕組み
リスクパリティ戦略の根本的な考え方は、株式や債券など異なる資産クラスが持つリスク特性を理解し、そのリスクを均等に配分することにあります。例えば株式は高いリターンを期待できる反面、価格の変動(ボラティリティ)が大きく、ポートフォリオ全体のリスクを大きく押し上げてしまいます。一方、債券は価格変動が小さく安定していますが、その分リターンも限定的です。
そこでリスクパリティでは、資産のボラティリティを基準に投資比率を調整します。変動の大きい株式の配分を減らし、比較的安定している債券の配分を増やすことで、両者がポートフォリオ全体に与えるリスクの寄与度を均等化します。たとえば、株式の変動が債券の3倍であれば、株式を30%、債券を70%といった形で調整するイメージです。
さらに、リスクの低い債券だけを増やすとリターンが低下してしまうため、レバレッジを活用して債券の投資額を拡大することも行われます。これにより、株式と債券がほぼ同じリスク寄与度を持ちながら、リターンを確保できる仕組みが成り立ちます。つまりリスクパリティ戦略は、「リスクのバランスを取るための比率調整」と「低リスク資産を補強するレバレッジ」の二本柱で構築されているのです。
リスクパリティ戦略のメリットとデメリット
リスクパリティ戦略の最大の強みは、分散効果の高さにあります。従来の資産配分では株式のリスクが大きく偏っていましたが、この戦略では株式・債券・コモディティといった異なる資産のリスク寄与度を均等にするため、特定の資産が大きく下落してもポートフォリオ全体への影響を抑えやすくなります。その結果、長期的には安定したリターンを期待でき、市場が大きく揺れ動く局面でも損失を軽減できる可能性があります。特に2008年の金融危機や2020年のパンデミックのような不確実性が高まる状況で、リスク分散の効果が注目されました。
一方で、リスクパリティ戦略にも注意点があります。安定性を高めるために債券を多く組み入れることが一般的ですが、金利上昇局面では債券価格が下落し、ポートフォリオ全体に悪影響を及ぼす可能性があります。また、低リスク資産のリターンを補うためにレバレッジを利用するケースが多く、この点が市場急変時にはリスクを拡大させる要因となり得ます。さらに、市場環境によっては株式比率を高めた従来の戦略の方がリターンが優れる場合もあり、必ずしも万能ではありません。
このように、リスクパリティ戦略は「安定性と分散効果」という大きなメリットを持つ一方で、「金利リスク」や「レバレッジリスク」といった側面を併せ持つ戦略です。そのため、導入にあたっては自身の投資目的やリスク許容度、そして市場環境を十分に考慮することが不可欠です。
実践方法
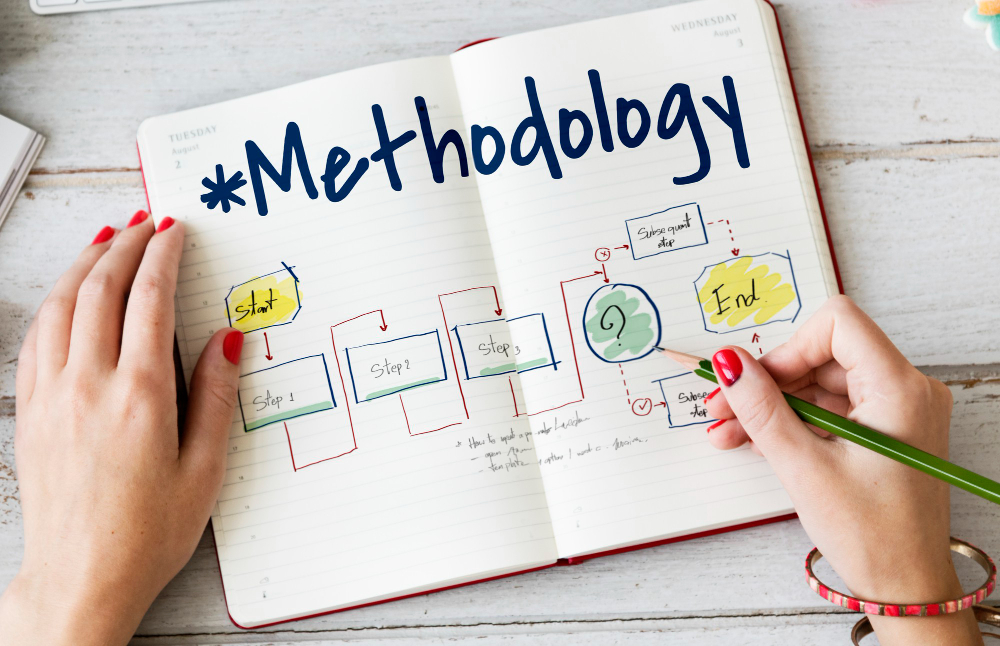
リスクパリティ戦略を実際に取り入れるためには、まず各資産のリスク寄与度を把握することが重要です。リスク寄与度とは、ポートフォリオ全体のリスクに対して各資産がどれだけ影響を与えているかを示す指標です。計算には資産ごとのボラティリティ(値動きの大きさ)や、資産間の相関関係を用います。例えば、株式のボラティリティが債券の2倍である場合、株式を少なめに、債券を多めに組み入れることで、両者がポートフォリオ全体に与えるリスクの寄与を均等に近づけることができます。実務ではエクセルや専用ソフトを用いて計算されますが、個人投資家向けにリスクパリティの考え方を反映したETFやファンドも提供されています。
具体的な商品例としては、米国市場で取引されている「リスクパリティ型ETF」や、世界的な運用会社が組成しているバランスファンドなどが挙げられます。これらはプロがリスク寄与度を計算・調整して運用するため、投資家は購入するだけでリスクパリティ戦略を間接的に活用することができます。日本国内でも一部の投資信託が類似の考え方を取り入れているケースがあり、海外ETFを利用する方法と合わせて検討可能です。
ただし実践にあたってはいくつかの注意点があります。まず、レバレッジを活用する場合は金利上昇によって借入コストが増加するリスクがあります。次に、定期的なリバランスが必要となる点です。時間の経過とともに資産の価格変動によってリスク寄与度がずれてしまうため、半年や1年ごとにポートフォリオを調整する必要があります。また、ETFや投資信託を利用する際には運用コスト(信託報酬やスプレッド)も考慮しなければなりません。
つまり、リスクパリティ戦略の実践は「リスクの測定」「分散の仕組みづくり」「継続的なメンテナンス」という3つの要素をバランスよく取り入れることが成功のカギとなります。
結論
リスクパリティ戦略は、従来のように資金を振り分けるのではなく、資産ごとの「リスクの大きさ」を基準にポートフォリオを構築する点に特徴があります。株式、債券、コモディティなどのリスクを均等化することで、特定の資産に依存せず、より安定したリターンを狙うことが可能です。長期投資を考える上で有効な分散手法の一つといえますが、レバレッジや金利環境といったリスク要因もあるため、自分のリスク許容度や市場状況を踏まえて慎重に導入を検討することが大切です。
免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。